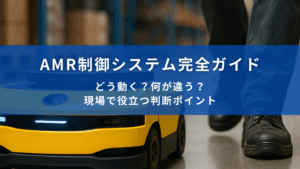近年、物流や製造の現場では人手不足や省人化の課題が顕在化しています。限られた人員で効率的に作業を回すため、ロボット導入はもはや選択肢ではなく「必須の施策」となりつつあります。特に、自律的に走行・搬送が可能なAMR(Autonomous Mobile Robot)は、人の代わりに荷物を運び、現場の生産性を大きく底上げする存在として注目を集めています。
しかし、AMRが真に現場で“使える”存在になるためには、安全性の担保が不可欠です。人やフォークリフトとすれ違うような混在環境でも、確実に障害物を検知し、柔軟に停止・回避できる能力が求められます。つまり、単に「走る」だけでは足りず、「環境を正確に認識する力」が必要なのです。
そこでカギとなるのが、LiDAR(Light Detection and Ranging)というセンサー技術です。LiDARは、AMRにとって“目”のような役割を担い、周囲をスキャンして障害物の有無や距離を瞬時に把握します。この記事では、そんなLiDARの仕組みから種類、AMRへの搭載時の活用方法や選び方まで、現場目線でわかりやすく解説していきます。
AMRの“目”となるLiDARの仕組みと種類をやさしく解説
LiDARの基本原理と構造
LiDAR(Light Detection and Ranging)は、対象に向けてレーザー光を照射し、その反射光が戻ってくるまでの時間差をもとに距離を算出するセンサーです。
この仕組みを利用することで、AMRは自らの周囲環境を立体的かつ高精度に把握できます。特筆すべきは、LiDARがカメラや超音波センサーとは異なり、光の速度を利用して「ミリ秒単位」で距離を測定できる点です。
そのため、障害物までの距離や形状を即座に認識でき、安全走行の根幹を支える「環境認識の中枢」として機能します。実際、多くのAMRではカメラやIMU(慣性センサー)などと連携しながらも、LiDARを中心に走行制御が構成されています。
AMRはセンサー構成だけでなく、「どう制御されているか」も導入の成否を左右します。制御の基本原理や各方式の違いを以下の記事でくわしく解説しています。
主なスキャン方式と分類
LiDARには、大きく以下の2軸で分類される方式があります。
スキャン方式の分類
- 2Dスキャン:主に水平方向にレーザーを照射し、平面的な障害物検知に特化
- 3Dスキャン:垂直方向も含めた全方位スキャンで、立体物の形状把握が可能
構造方式の分類
- 機械式(メカニカル):回転部を持ち、広範囲をカバーできるが、摩耗や振動の影響を受けやすい
- ソリッドステート:可動部を持たず、耐衝撃・耐振動性が高く、メンテナンス負荷が小さい
2Dタイプは部品点数が少なく価格も抑えられるため、コスト重視の屋内環境で多用されます。例えば、倉庫内で棚の間を移動するAMRでは、床面に落ちた工具や台車を認識し、スムーズに避けるための用途に適しています。
一方で3Dスキャンやソリッドステート型は、屋外搬送や人と協働する環境において活躍します。段差・傾斜・視線の高さがバラつくような空間では、垂直方向の検知精度が安全性を左右するためです。たとえば、屋外で工事資材を搬送するAMRでは、日光や風雨の影響にも強いセンサー構造が求められます。
AMRに多く採用されるタイプとは?
多くのAMRは、使用環境に応じてLiDARの方式を選定しています。以下はその代表例です。
- 屋内(物流倉庫、製造工場):2Dスキャン+機械式
→ コストと検出精度のバランスが良く、比較的安定した環境下での搬送に最適 - 屋外や混在環境(建設現場、病院内物流):3Dスキャン+ソリッドステート
→ 耐環境性と立体把握力が求められ、可動部のない構造が長期運用にも適する
実際の運用現場では、「同じ空間で人とロボットがすれ違う」「搬送対象が大きく揺れる」「反射率の低いマット素材が床に敷かれている」といった状況にも柔軟に対応する必要があります。そのため、LiDARのスペックだけでなく、スキャン範囲の配置設計や他センサーとの組み合わせも含めた総合的な判断が不可欠です。
このように、LiDAR選定においては“構造だけを見る”のではなく、“運用環境とリスク要因をどう制御できるか”という視点が重要です。リードエンジニアや現場責任者とのすり合わせを通じて、実運用に適した設計を早期から取り入れることが、AMR導入成功のカギとなります。
AMRが安全に動ける理由とは?LiDARの用途と活用イメージを解説
LiDARの役割:AMRの「視覚」としての中核機能
自律移動ロボット(AMR)は、固定されたガイドや磁気テープに依存せず、自ら周囲を認識して柔軟に走行ルートを判断することが求められます。そのためには、単に「障害物を避ける」だけでなく、周囲の空間を正確に把握し、「今どこにいるか」「次にどこへ向かうか」をリアルタイムで認識する能力が必要です。
ここで中核となるのがLiDARです。LiDARはAMRにおける“視覚”として、以下の3つの重要な役割を果たします。
| 機能領域 | LiDARが担う役割の具体例 |
|---|---|
| 障害物検知 | 人や物体をリアルタイムに検知し、回避・停止を制御 |
| 自己位置推定(SLAM) | 周囲の構造物との相対位置を把握し、現在地とマップを同時に生成 |
| 安全性の補完 | 他センサー(カメラ・超音波)と組み合わせて死角を最小化 |
これらの機能が統合されることで、AMRは変化の多い現場でも柔軟かつ安全に稼働できるようになります。
AMR構成におけるLiDARの配置例
以下はAMR本体とLiDARの配置関係を簡略化した構成図です。前方だけでなく側面・背面にもセンサーを設けることで、360度の安全性が確保されます。
┌─────────────┐
│ LiDAR(前方)│ ← 進行方向をスキャン
└─────────────┘
↑
┌─────────────────┐
│ AMR本体(走行ユニット) │
└─────────────────┘
↑ ↑ ↑
LiDAR(左) LiDAR(背面) LiDAR(右)← 周囲の死角をカバー設置位置の工夫により、衝突リスクが高い方向を重点的に監視する構成も可能です。たとえば、出入口や交差ポイントに強い前方LiDAR、後退時に必要な背面LiDARなど、シーンに応じて柔軟な配置が求められます。
SLAMとの連携で実現する「自己判断型ナビゲーション」
LiDARは単独でも高精度の距離情報を提供できますが、さらに大きな役割を果たすのが「SLAM(自己位置推定と地図生成)」との連携です。
SLAMでは、LiDARで取得した周囲の形状データをもとに、AMRがその場でマップを構築し、かつ自分の位置をリアルタイムに追跡します。これにより、以下のような現場課題を解決します:
- 環境が固定されていない(仮設レイアウト・可動棚など)
- 一時的な障害物が存在する(作業員や台車など)
- 屋外・半屋外などでGPSが使えないエリア
この自己判断型ナビゲーションは、特にレイアウトが日々変化する倉庫や、複数AMRが連携して動く現場において極めて有効です。
SLAMの方式別の違いや導入時の判断ポイントについては、こちらの比較解説記事も参考になります。
運用現場のニーズに応じた配置・設計が鍵
AMRにおけるLiDAR活用は、「取り付けて終わり」ではありません。検知範囲・角度・高さといった設計要素が、稼働後の性能を大きく左右します。以下のようなポイントを事前に確認することで、トラブルの少ない運用が実現できます。
- 棚下や床面の低い障害物まで検知できる高さに配置されているか?
- 回転部の有無によるメンテナンス頻度に現場体制が対応できるか?
- 他のセンサー(カメラ・超音波)との組み合わせで冗長化されているか?
このように、LiDARは「見える」だけでなく、「考えて動く」AMRにとって欠かせない存在です。環境・目的・運用者スキルまで含めて最適化された設計こそが、真に現場で“使える”AMRの条件となります。
LiDARが活用される「自己位置推定・地図生成(SLAM)」の仕組みについては、AMRのSLAM技術とは?自己位置推定とマッピングの仕組みをわかりやすく解説で詳しく解説しています。
AMR導入で失敗しないために──LiDAR検討のベストなタイミングとは?
AMR(Autonomous Mobile Robot)の導入は、単に機器を導入するだけで完結するものではありません。重要なのは「現場の課題解決に直結する機能を、必要な性能と仕様で確保する」ことであり、その中でもLiDARの選定と導入タイミングは安全性・精度・コスト効率に直結するクリティカルな要素です。
特に、AMRの“走行精度”と“事故回避能力”を支えるLiDARは、現場環境との適合性を高い次元で求められるため、設計初期からの検討が不可欠です。
なぜ早期検討が重要なのか?
LiDARの検討を後回しにすると、「AMRは届いたが、現場の棚配置では死角が多すぎる」「床材の反射率が低く、うまく障害物を認識できない」といった事態に陥りがちです。こうした“想定外”は、後工程での機器再選定・レイアウト変更・追加費用発生など、プロジェクト全体の遅延とコスト増加に直結します。
逆に、導入初期からLiDARの必要条件を明確にし、それに基づいた選定・配置・運用設計を行えば、AMR導入のROI(投資対効果)は大きく改善します。
各フェーズにおけるLiDARの検討ポイント
- 要件定義段階での戦略設計
ここで重要なのは「どこを走るのか」ではなく「何を回避すべきか」「どんな作業者とすれ違うのか」といった具体的な運用シーンを設計に落とし込むことです。
たとえば、人の往来が激しい通路ではLiDARの検知速度が、屋外搬送があるなら防塵・防滴性能が、暗い倉庫では反射性能が求められます。
- 機器選定段階での性能照合
スペック表だけでなく、「検知できなかったときのリスク評価」まで含めて選ぶべきです。重要なのは“最高性能”ではなく、“現場で過不足ない性能”を持つこと。これは多くのAMR導入失敗事例で共通する盲点です。
- 実証実験段階での動作確認
可能であれば現場レイアウトの簡易マップを用い、AMRの走行テストを事前に実施しましょう。
このとき、「検出ログを記録できるモデル」であれば、どの位置でどの対象をどう検知したかを後から分析でき、運用設計の精度が飛躍的に高まります。
- 導入・運用段階での保守体制整備
LiDARは光学機器であるため、埃や傷の影響を受けやすく、定期清掃・キャリブレーション(較正)ルールの整備が欠かせません。
また、現場スタッフが簡単にメンテできる構造か、故障時の代替対応が可能かといった視点も、長期運用では重要です。
フェーズ別確認項目(表)
| 導入段階 | 検討すべきLiDAR項目 |
|---|---|
| 要件定義 | 使用環境(屋内/屋外)、作業者との距離、安全基準 |
| 機器選定 | 種類(2D/3D)、視野角、検知距離、IP規格、反射率対応 |
| 実証実験 | 死角の有無、反射しない物体の検出、データログ取得 |
| 導入・運用 | 清掃頻度、校正方法、交換性、障害時の冗長構成 |
特に見落としがちなのが、実証実験段階での“死角検出”や“反射しにくい物体への対応”です。倉庫内の黒い台車や透明なビニールカーテンなど、LiDARが検知しづらい対象が実際の現場には多く存在します。これらを導入前にテストしておくことで、導入後の手戻りや運用トラブルを未然に防ぐことができます。
実運用を見据えたLiDAR選定がAMR成功の鍵
センサーの選定は「AMRがどこまで安全に、どれだけ柔軟に使えるか」を左右する基盤技術の判断です。LiDARの検討を単なる機器選定ではなく、現場ニーズの深掘りと再現性のある設計にまで落とし込むことで、AMRは真に現場にフィットする“戦力”になります。
導入フェーズを「調達作業」としてではなく「価値を最大化する工程」と捉え、早い段階からLiDARの目線で現場を見つめ直すことが、AMR導入成功の第一歩です。
AMR導入の成否を分ける!LiDAR選定時に押さえるべき5つのポイント
AMRの性能や安全性を左右するLiDARの選定は、単にスペックの高い製品を選ぶという話ではありません。現場の環境や運用シナリオにマッチしているかどうかが最重要であり、「適切な製品を、適切な理由で選ぶ」ための視点が不可欠です。
以下では、LiDAR選定時に必ず確認しておくべき5つのチェックポイントを、現場目線で具体的に解説します。
チェックポイント① 検知距離
LiDARの検知距離は、障害物への反応速度と安全性を直接左右します。たとえば、通路が狭く交差点が多い倉庫では、最低でも5m以上の検知範囲が必要とされるケースが一般的です。
検知距離が短すぎると、作業員の急な飛び出しに反応できず衝突リスクが高まります。逆に、長距離対応の製品を選びすぎると価格や本体サイズが過剰になりがちです。重要なのは、「回避動作に必要な距離」から逆算する設計視点です。
チェックポイント② 視野角
視野角は、LiDARがどの程度の範囲を一度にカバーできるかを示す指標です。たとえば、270°カバーする製品であれば前方〜側面まで1台で監視できますが、180°未満では死角が発生しやすくなります。
以下のような構成図で、死角の発生位置を把握しておくと選定ミスを防げます。
<LiDAR視野カバー例(上から見た図)>
┌───────────────┐
│ カバー範囲(270°) │
└──────┬───────┘
│ ← 死角(90°)方向チェックポイント③ 防水・防塵性能(IP規格)
屋外や粉塵の多い製造現場では、IP等級の確認は必須です。IP65以上が一つの目安で、これに満たない場合、雨や水しぶき、粉塵によってLiDARの精度が劣化するリスクがあります。
たとえば、屋外の搬送ラインでLiDARが泥はねを受けて停止した事例もあるため、「設置場所のリスク環境を先に定義」することが重要です。
チェックポイント④ 他センサー・SLAMとの連携
LiDARは単体で使われるケースは少なく、カメラ・超音波・エンコーダとの連携や、SLAMとの統合が前提になることが多いです。
したがって、通信プロトコル(Ethernet/CAN/RS232など)や、SLAMソフトとの互換性は事前に確認しておくべきです。「検知性能」だけでなく、「統合性」も選定基準にすることが、現場トラブルの回避につながります。
チェックポイント⑤ 取り付け性と重量
LiDARのサイズや重量も見落とされがちな要素です。AMRの設計によっては取り付けスペースが限定されていたり、重心バランスへの影響が出ることもあります。
特に、コンパクト設計のAMRでは「取り付け不可」や「振動で精度低下」などの問題が発生するため、事前にCAD図面ベースで干渉チェックを行うのが理想です。
単なる比較ではなく「適合性評価」が肝
下記に主要項目を整理した表を再掲します。複数製品を比較する際は、価格やスペックだけでなく、自社のAMR環境にどれだけフィットするかという「適合性評価」が重要です。
| チェック項目 | 選定時の判断基準例 |
|---|---|
| 検知距離 | 最低5m以上か、回避動作に間に合う距離か |
| 視野角 | 死角を作らずに必要範囲をカバーできるか(180°以上推奨) |
| 防水・防塵(IP) | IP65以上か、粉塵・水滴が多い環境に対応できるか |
| センサー・SLAM連携 | 他センサーと連動可能か、既存ソフトと通信互換があるか |
| サイズ・重量 | AMRに物理的に搭載できるか、重心への影響が出ないか |
LiDARは単なる“部品”ではなく、AMRの安全性・知覚力を左右する「神経系」と言っても過言ではありません。だからこそ、選定には設計・現場・運用の三者での検討が必要です。価格やブランド名に惑わされず、自社の現場に最適な選定を行うことが、長期的な安定運用への最短ルートです。
AMR運用で後悔しないために──LiDARに関するよくあるトラブルと対策
LiDARはAMRの“目”として極めて高精度な距離計測を実現しますが、現場での運用においては「センサーだからこそ起こる盲点」が存在します。見た目では分かりづらいトラブルが、搬送ミスや接触事故といった重大な結果を引き起こすこともあるため、リスクと対策を事前に理解しておくことが重要です。
よくある誤検知・検出漏れのパターン
LiDARの仕組み上、以下のような対象物に対しては正確な反射信号が得られにくく、誤検知や見落としが起こりやすくなります。
| 対象物の例 | 起きやすい現象 | 原因となる性質 |
|---|---|---|
| 黒色のゴムマット | 距離が正常に取れない | 光吸収率が高く、反射光が弱い |
| ガラス扉・透明カーテン | 存在を検知できない | レーザーを透過してしまう |
| 光沢のある金属棚 | 位置が誤って表示される | 反射が強すぎて複数経路が混在する |
このような検出エラーが頻発すると、「AMRが停止しない」「回避動作が遅れる」といったトラブルが発生します。特に混在環境では、AMRが誤った位置推定をして誤進入するケースもあり、センサー特性の理解が重要です。
LiDARの誤検知リスクゾーン
[AMR走行方向 →]
▓▓▓(黒い床マット)→ 検知しづらい
┃ ┃(ガラス壁) → 透過で無視される
◯ ◯(人/障害物) → 正常検知される
※誤検知ゾーンでは停止反応が遅れるリスクメンテナンスと運用の工夫でトラブルを最小化
LiDARは精密機器であるため、運用面でのちょっとした配慮が性能維持に大きく影響します。以下は、実務で効果的な対策例です。
| 運用対策 | 実施目的 |
|---|---|
| レンズ清掃を日次チェック項目に追加 | 水滴・埃による反射異常の防止 |
| 清掃用クロスの専用品を用意 | 傷・静電気による誤作動を防ぐ |
| 通信/電源ラインの冗長構成 | トラブル発生時もフェールセーフで稼働 |
| センサーエリアに遮蔽物を設けない | 定常的なスキャン妨害の排除 |
また、LiDARの異常をログで確認できる機能を持つ製品であれば、「何が原因で停止したのか」を後から検証しやすく、再発防止策の立案にも役立ちます。
安全運用のカギは「予防的メンテナンス」と「リスクの可視化」
LiDARの導入効果を最大化するには、単に高性能なモデルを選ぶだけでは不十分です。環境特性を理解し、検知精度を維持するための運用設計を整えることが、AMRの安全性と稼働率を維持するためのカギです。
特に初期段階では、障害物認識テストを通じて「見落としやすい対象」を洗い出し、検出エリアの最適化やセンサー配置の調整を行うことが、長期的なトラブル回避につながります。LiDARの誤検知は一見わかりにくいトラブルですが、それを“見える化”し、運用に反映できるかが、安全なAMR運用を実現する分水嶺となります。
その課題、LiDAR搭載AMRで解決できるかもしれません
AMRを導入する目的は、単なる自動化ではなく、現場の安全性・効率性・柔軟性を向上させることにあります。特に、LiDARを搭載したAMRは“認識力”と“判断力”に優れ、変化の多い作業現場においてその真価を発揮します。
以下のような課題を抱える現場では、LiDAR搭載AMRの導入が有効な解決策となる可能性があります。
課題① 作業者とAMRが同じ空間に共存しており、接触リスクが心配
人とロボットが同じフロアを移動するような協働環境では、接触事故のリスクが常につきまといます。LiDARは人の動きをリアルタイムに検出し、スピード調整や停止指令を即座に行えるため、安全柵の設置が難しい現場でも高い安全性を確保できます。
[協働環境イメージ]
作業員 → ← AMR
▲ ▲
| ← LiDARが相互認識課題② 棚・台車など可動物が多く、静的マップでは対応できない
倉庫や工場では、日々の作業によって棚の位置や荷物の状態が変化します。こうした「常に変わる現場」では、LiDARによる動的な障害物検知とルート再構築(リアルタイムSLAM)が大きな効果を発揮します。
| 現場の特徴 | 従来型AMR | LiDAR搭載AMR |
|---|---|---|
| 棚の移動が日常的にある | 衝突リスクが高まる | 自動で経路再計算・回避行動が可能 |
| 不定形の障害物がある(人・荷物) | 検知できず立ち往生する | 形状・距離を即座に判断し安全に停止 |
課題③ 屋外や開放空間での搬送が求められる
雨風や日光、段差・傾斜のある環境では、カメラや超音波では認識が不安定になりがちです。LiDARは光の反射時間で距離を測るため、明るさや反響音に依存せず、屋外でも安定して動作します。
加えて、IP等級の高いソリッドステートLiDARなら、水滴や粉塵への耐性も備えており、全天候対応型のAMR運用が実現できます。
課題④ マップ生成や自己位置推定を精度高く行いたい
SLAM技術を使った自己位置推定とマップ作成において、LiDARは最も信頼性の高いセンサーの一つです。以下のような用途において、LiDARの導入価値は特に大きくなります。
- レイアウト変更が頻繁にある工場で、都度マップ修正が発生する
- 正確な位置把握が必要な工程間搬送を行う
- 既存のGPSが使えない屋内空間での高精度ナビゲーション
判断の目安:LiDAR搭載AMRが効果的な現場チェックリスト
☑ 作業員との協働エリアで接触リスクがある
☑ 障害物が可動/不定形/不規則に変化する
☑ 屋外や半屋外での運用を想定している
☑ マップ更新・自己位置推定の精度が運用に直結する
☑ 他センサーだけでは死角や誤検知が生じているこれらの条件に複数該当する場合、LiDAR搭載AMRの導入は単なる「自動化」ではなく、「現場の変化に強く、事故を防げる運用体制の構築」に直結します。
LiDARは、高性能ゆえに導入コストも一定かかるセンサーですが、長期的に見れば安全性・柔軟性・可用性の面で得られるリターンは非常に大きなものです。単なる“ハイスペック”としてではなく、「現場の課題解決に合致する戦略的選択」として導入を検討することで、AMR導入の成功確率は確実に高まります。
AMR導入を成功させるためのLiDAR活用設計のポイント
LiDARはAMRの“目”として障害物検知や自己位置推定を担う重要なセンサーですが、それ単体の性能だけでAMRの効果が最大化されるわけではありません。真に現場で“使える”AMRを設計するには、センサー設計とAMR本体の制御・運用設計の最適な連携が不可欠です。
ポイント①:LiDAR性能だけでなく「配置と角度」で決まる現場精度
LiDARの仕様書に記載された視野角や検知距離が理想的でも、実際の設置位置や角度によって検知範囲は大きく変わります。たとえば、床面ギリギリを走る小型障害物を見落とすケースや、搭載位置が高すぎて人の足元を検知できないケースが典型的です。
【LiDARの検知エリアと取り付け位置の関係】
LiDAR設置位置:高すぎる → 足元が死角に
↓
┌──────┐
│ AMR本体 │
└──────┘
↓ ↓
△←障害物(低位置)→未検知
対策:低めの角度 or 傾斜設置で床面までカバーこのように、設置高さ・角度・傾斜方向のシミュレーションを事前に行うことで、誤検知や検出漏れのリスクを大きく減らせます。
ポイント②:AMR本体の制御系との連携性が“安全判断の速度”を左右する
LiDARは検知結果をリアルタイムでAMR本体に送信し、減速・回避などの判断を下します。このプロセスにおいて、センサーデータの処理速度とAMR制御系の応答性の連携が取れていないと、以下のような問題が起こります。
| 検知→制御の連携が不十分な場合のリスク |
|---|
| 障害物発見後の停止が遅れる |
| 本来必要ない回避動作が頻発する |
| 不自然なブレーキ挙動が作業者に不安を与える |
そのため、LiDARの出力仕様(データ更新周期、通信形式)とAMR制御系の入力処理能力の整合性を確認し、リアルタイム制御を阻害しない構成を事前に設計することが重要です。
ポイント③:他センサーとの“役割分担”による死角補完と安定化
LiDARは距離測定に非常に優れていますが、全方位を完全にカバーできるわけではなく、黒い物体・透明素材・低反射面には弱いという特性があります。そこで、他センサーとの役割分担・補完設計が効果的です。
| センサー | 主な得意領域 |
|---|---|
| LiDAR | 距離・形状の検知、SLAM、動的障害物対応 |
| カメラ | 色認識、QRコード・物体識別 |
| 超音波センサー | 近接警戒(0.1〜1.0m)、低速時補完用 |
| エンコーダ | 自己位置追跡、走行距離計算 |
たとえば、進行方向はLiDAR、側面は超音波、後方はカメラによる画像監視など、リスクの高い方向ごとにセンサーを適材適所で配置することで、運用の信頼性が大きく向上します。
センサー統合設計こそが「安全で止まらないAMR」の鍵
LiDARはAMRの目であると同時に、現場の安全文化や効率を担保するインフラです。単体の性能だけを追いかけるのではなく、「どの位置に、どの角度で、どの他センサーと連携させるか」という統合的な設計視点を持つことが、AMR導入を“投資から価値”に変える最大のポイントです。
導入時にはLiDAR単体の評価にとどまらず、制御設計・筐体設計・清掃体制までを含めた“AMR全体アーキテクチャ”としての整合性を検証することが、失敗を防ぎ、現場への定着を加速させます。
AMRの価値を最大化するLiDAR活用──導入前に押さえるべき本質とは
LiDARは、AMRが単なる移動機械ではなく、「環境を理解し、自律的に判断・行動するインテリジェントな存在」となるための中核センサーです。障害物の検知から自己位置推定、死角の補完まで、あらゆる局面でAMRの“視覚と判断”を支える技術として、今やなくてはならない存在となっています。
しかし、LiDARは“高性能=最適”とは限りません。走行環境、協働対象、可視範囲、搬送精度、保守体制といった複数の要素を加味し、「自社の現場において最大限の価値を発揮するかどうか」という視点で選定・設計することが重要です。
そのためには、次の3点を重視すべきです:
- 運用環境に即したLiDARスペックの選定(距離・視野・IP等級など)
- AMR本体とのリアルタイムな制御連携(応答速度と通信仕様の整合)
- センサー全体設計としての統合性(カメラや超音波との補完)
導入フェーズだけでなく、運用・保守フェーズも見越して最適化されたLiDAR活用戦略は、事故を未然に防ぎ、止まらないAMR運用を実現する基盤となります。製品スペックだけにとらわれず、AMRとの“チーム設計”という発想でセンサーを選ぶことが、真に成果につながる導入判断です。
LiDARの仕組みやセンサー構成、安全設計の考え方までをやさしく解説した AMR導入まるわかりガイド を無料配布中です。自社の安全要件や現場環境に合ったセンサー選定の判断材料として、ぜひご活用ください。