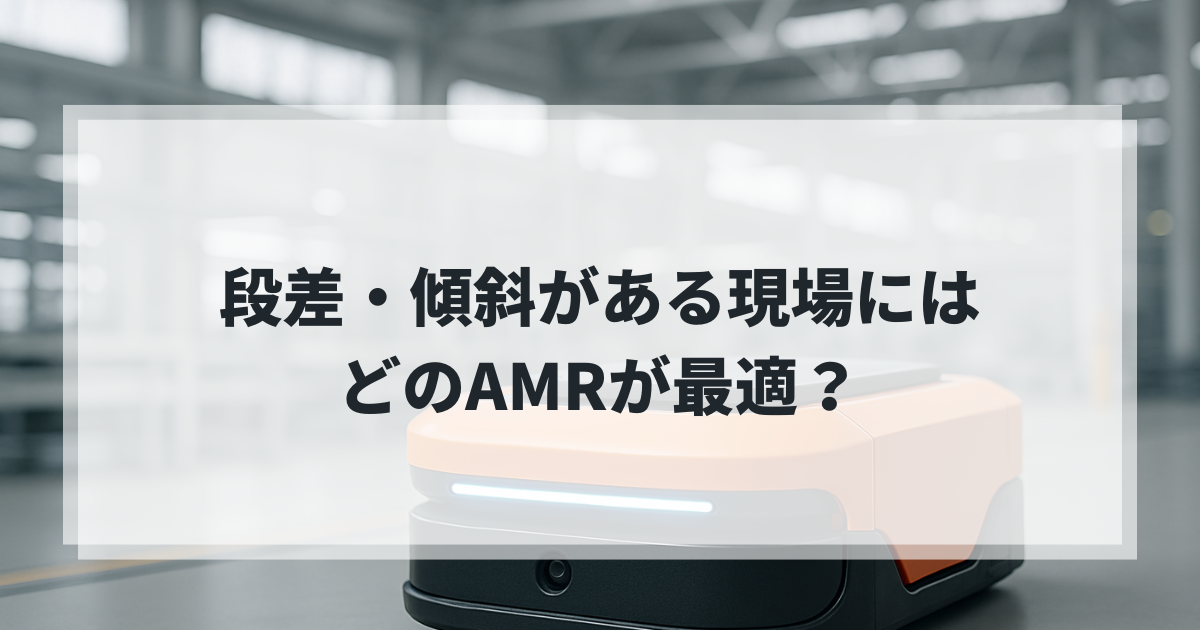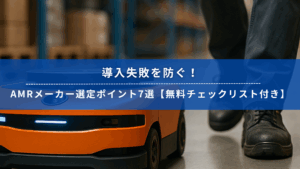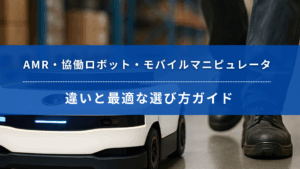段差や傾斜のある現場にAMRを導入したのに、「なぜか止まる」「想定より登れない」──そんな声を現場で聞いたことはありませんか?
実はその“うまくいかない理由”、多くの場合がスペックではなく「選定ミス」。
つまり、走破性の高さではなく、“どんな段差や傾斜に強いか”という相性の見極めにこそ、成否の分かれ道があります。
この記事では、現場環境に応じてどんなタイプのAMRが合うのかを、走破性の観点から診断形式でわかりやすく整理。
「スペックだけでは選びきれない」という導入担当者の悩みに、具体的な判断軸を提供します。
停止・空転・故障──実際のAMRトラブルから見る現場の課題
「動くはず」が動かない理由とは?
AMRの導入が進む工場や物流センターにおいて、「スペック上は対応できるはずの段差や傾斜で止まる」「荷物を積んだ途端に空転する」といったトラブルが現場から多く報告されています。とくに屋外環境や傾斜通路のように変化のある地形では、AMRの走破性が設計段階での想定を裏切るケースが少なくありません。
このような現象の多くは、単なる出力不足や製品の欠陥ではなく、「環境との相性を見誤った選定ミス」によるものです。
トラブルの構造を分解する:地形とAMR構成の相互作用
AMRが停止・空転・故障を起こす主な要因は、以下のように複数の構造要素と環境要素の組み合わせによって発生します。
| トラブル現象 | 主な原因 | 環境要素 | 構造要素 |
|---|---|---|---|
| 段差で停止 | 段差の高さ+アプローチ角の組み合わせ | 段差前の傾斜・床硬度 | タイヤ径・サスペンション構造 |
| 傾斜で登れない | 登坂力不足/片輪空転 | 傾斜角・滑りやすい床材 | 駆動輪数(2WD/4WD)・トルク性能 |
| 空転して進まない | 摩擦係数の低さ | 湿潤床面・金属床など | タイヤ素材・重量配分 |
| 自己位置喪失 | センサー誤認 | 反射率の高い壁/屋外の電波干渉 | LiDAR方式・GNSS精度 |
このように、同じトラブルでも発生原因は多岐にわたります。重要なのは、「現象の背景にある構造と環境の組み合わせ」を見極めることです。
段差や傾斜だけでなく、「搬送エリア」や「搬送物の重さ」など、AMR選定には複合的な視点が欠かせません。
現場タイプ別に最適なAMRを見極めるための5つの判断軸を、より詳しく知りたい方は下記ガイドをご覧ください。
全方向タイヤの“利便性”が逆にリスクになるケース
たとえば、全方向駆動タイヤは方向転換の自由度が高く、狭小スペースでの運用に適しています。しかしこの構造は、段差を越えるための押し出し力が弱く、路面との接地面積が小さいため滑りやすいという欠点があります。実際に、樹脂製タイルや微細な傾斜でも停止してしまう事例が報告されています。
また、全方向タイヤはタイヤの摩耗による性能劣化も早く、特に床材が硬い場所では想定よりも早期に動作不良を起こすことがあります。
AMR設計と現場環境の“マッチング精度”が稼働率を左右する
AMRのパフォーマンスを最大化するには、カタログスペックの理解では不十分です。必要なのは「設計スペック × 実地環境」のマッチング精度を高めることです。そのためには、次のような確認ステップが推奨されます。
- 段差や傾斜の構造的特徴(高さ・角度・床素材)を詳細に可視化
- 過去に同環境で導入されたAMR事例の挙動データを収集
- デモ機でのテスト走行により“設計値と現場の乖離”を確認
屋外や傾斜のある現場におけるAMR導入の費用対効果を高めるポイントについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
トラブルの予兆は“構造と環境のミスマッチ”に現れる
AMR導入時の失敗要因は、見た目やカタログ数値だけでは判断できません。停止や空転といったトラブルを回避するには、「どんな地形に、どんな構造のAMRが合うのか」を事前に正しく見極める仕組みが必要です。単なるスペック比較ではなく、実際の運用条件とのマッチング精度こそが、安定稼働と費用対効果を左右します。
AMRの走破性に影響する主な要素とは?
タイヤ構造(全方向・エアタイヤ・クローラーなど)
タイヤ構造は、AMRが地形を乗り越える力に直結します。たとえば、クローラー式はキャタピラのように地面をつかみながら進むため、段差や傾斜でも滑りにくく、悪路走行にも対応可能です。一方、全方向タイヤはスムーズな回転が得意で屋内では便利ですが、段差を乗り越えるには不向きです。現場の床材や凹凸の有無によって、最適な構造は大きく変わります。
駆動方式と出力(2WD/4WD、登坂力)
AMRの動力源は走破性に直結します。特に傾斜がある現場では、登坂力やトルク性能が求められます。2WDは軽量で消費電力も抑えられますが、4WDのように左右独立した動作ができないため、登坂時に片輪が滑ると立ち往生する可能性があります。傾斜の角度だけでなく、荷重や滑りやすい路面との組み合わせにも注意が必要です。
センサーと地形把握能力(RTK、LiDARの違い)
傾斜や段差を正しく認識し、適切な制御を行うには、AMRに搭載されたセンサーの性能が鍵を握ります。LiDARは屋内での位置推定に優れ、物体との距離測定に強い一方、屋外では反射率や天候の影響を受けやすいです。GNSSとRTKを組み合わせることで、屋外でも高精度な自己位置推定が可能になり、複雑な地形でも正確な走行が実現します。
| 要素 | タイプ | 特徴/メリット | 対応環境例 |
|---|---|---|---|
| タイヤ構造 | クローラー | 段差乗り越えに強い | 屋外/不整地 |
| エアタイヤ | 衝撃吸収・滑りにくい | 傾斜/段差あり | |
| 全方向タイヤ | 小回りが利くが段差に弱い | 屋内の平坦路 | |
| 駆動方式 | 2WD | 軽量・省エネ | 屋内/軽搬送 |
| 4WD | 登坂・滑りに強い | 傾斜・段差の多い現場 | |
| センサー | LiDAR | 幅広い認識、天候に比較的強い | 屋内・屋外両用 |
| RTK+GNSS | 屋外特化、高精度位置制御 | 屋外全般 |
AMRの構造的な違いだけでなく、メーカーごとの特徴や選定時の注意点も確認したい方は、こちらの記事をご覧ください。
環境タイプ別|最適なAMRタイプ診断フロー
段差や傾斜といっても、その組み合わせや使用環境は多様です。以下のフローチャートから、自社に合ったAMRの走破性タイプを診断してみましょう。現場環境に応じて、どの構成要素を重視すべきかが明確になります。
[現場は屋外か?]──はい→[舗装されている?]──はい→[段差がある?]──はい→[4WDタイプAMR]
└──いいえ→[全地形対応AMR(クローラー)]
└──いいえ→[通路傾斜あり?]──はい→[登坂性能重視タイプ(大径タイヤ+4WD)]
└──いいえ→[一般型AMR(全方向駆動可)]AMR以外の自律型ロボット(協働ロボットやモバイルマニピュレータ)との違いや選定ポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
AMR選定時に見落としがちな比較ポイント
カタログスペックに潜む“現場非対応”の罠
AMRの導入時、カタログに記載された「最大段差30mm」「登坂能力10度」といった数値だけを見て判断するのは非常に危険です。なぜなら、これらの数値は理想的な試験環境での性能であり、実際の現場とは条件が大きく異なるからです。
たとえば、段差の手前に小さな傾斜があるだけで、実際には車輪が乗り上げにくくなり、滑って登れないケースもあります。また、床面が滑りやすい素材であれば、十分なトルクがあっても空転してしまうことがあります。さらに、荷物を積載した状態では駆動力が低下するため、無積載時のテストだけでは判断できません。
このように、「数値通りに走るとは限らない」ことを前提に、現場テストやシミュレーションを必ず実施する必要があります。とくに段差や傾斜がある環境では、設計図面だけでなく実地での検証が極めて重要です。
構造の違いが“実性能差”に直結する
同じようなスペックを持つAMRでも、構造によって対応力には大きな差が出ます。たとえば、クローラータイプとエアタイヤタイプはどちらも段差走破性に優れていますが、路面との接地圧や衝撃吸収力に違いがあるため、長距離搬送時の安定性やメンテナンス性に差が生まれます。
以下は、代表的なAMRモデル3種を簡易的に比較した表です。それぞれの得意環境や特性を把握することで、自社の導入判断に役立ちます。
| モデル名 | 対応地形 | 最大段差 | 登坂能力 | タイヤ構造 | センサー方式 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model A | 舗装/屋外 | 30mm | 10度 | エアタイヤ | LiDAR+RTK | 雨天対応 |
| Model B | 不整地/屋外 | 50mm | 15度 | クローラー | GNSS+RTK | 全地形対応 |
| Model C | 屋内 | 10mm | 5度 | 全方向 | LiDAR | 小型/狭小スペース対応 |
このような比較は、単なる“数値スペックの並列”ではなく、現場ごとの制約条件を念頭に置いて読み解く必要があります。実績あるモデルであっても、構造の違いが稼働率やトラブル率に直結するため、安易なスペック比較には注意が必要です。
まとめ|AMRの導入は、まずは「環境」と「走破性」から逆算しよう
走破性の誤判断は、導入後のトラブルにつながりやすい要素です。段差や傾斜は、AMRにとって「越えられるかどうか」の重要な壁です。自社の環境(屋外か、傾斜・段差の有無、舗装状況など)を見極めたうえで、AMRの走破性能とマッチしているかを選定段階から丁寧にチェックしましょう。
資料ダウンロード|「このタイプで本当に走れるのか?」を確認する前に
段差や傾斜に強いAMRを選んだはずなのに、
「現場では登れない」「止まってしまう」──そんな声が後を絶ちません。
選定時の判断を確かなものにするには、“現場目線”で選ぶための基準が必要です。
この資料では、走破性トラブルの原因となる“見落としポイント”や、タイプ別の適合条件を整理。
導入の一歩手前で「本当に合っているか?」を見極めるチェック項目も掲載しています。
「このまま選んで大丈夫か不安」──そう感じた方は、まずこの資料をお手元に。