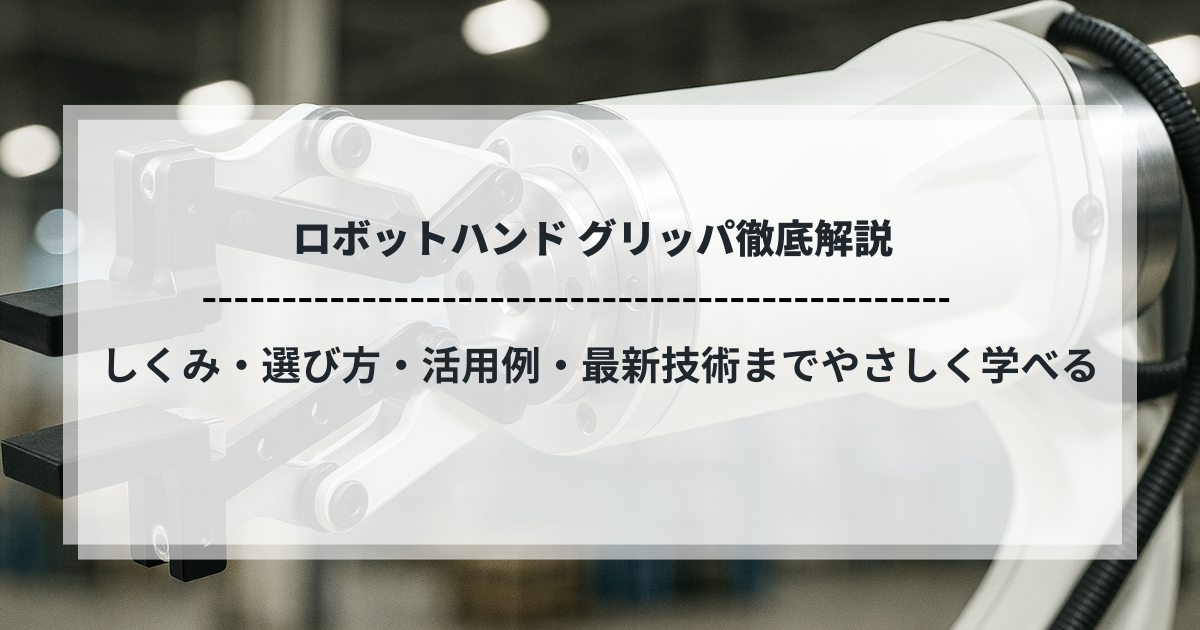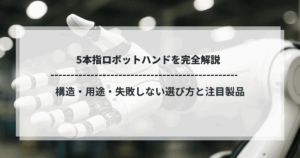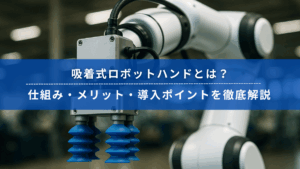ロボットによる自動化を進めたいと考えていても、「どのグリッパを選べばいいのかわからない」「ハンドとの違いがあいまいで判断に迷う」と感じたことはありませんか?
特に製造・物流・食品・医療といった現場では、ワークの材質や形状が多種多様であるため、適切なグリッパを選ばなければ作業効率や品質に大きな影響を及ぼします。
こうした悩みを解消するためには、ロボットハンド グリッパの構造や制御方式、用途ごとの適性を体系的に理解し、自社の条件に合った選定軸を持つことが重要です。
なぜなら、グリッパは単なる「つかむ道具」ではなく、力加減や動作速度、衛生対応、制御精度など、多くの要素が関係する複雑な機構で構成されており、選び方ひとつで導入効果が大きく変わってくるからです。
この記事では、ロボットハンド グリッパの基本構造と仕組み、ハンドとの違い、駆動方式ごとの特徴、用途別の選定ポイント、さらにAIやセンシング技術による最新動向まで、現場で役立つ視点からわかりやすく解説します。
読み終えるころには、自社に最適なグリッパの選び方が明確になり、導入や改善の判断に自信を持てるようになります。
ロボットハンドグリッパの基本概念|基本的な仕組みと役割
ロボットハンドグリッパとは何か?
ロボットハンドグリッパとは、産業用ロボットの先端に取り付けられ、物体をつかむ・持ち上げる・移動させるといった作業を行う装置です。人間の手のような役割を果たし、製造業や物流業界などで幅広く活用されています。特に自動化が進む現場では、繊細な部品の取り扱いや高速なピッキング作業に欠かせない存在です。
このグリッパは、単なる「ロボットの手」ではなく、対象物の形状や材質に応じて最適な把持方法を選べるよう設計されています。例えば、柔らかい食品をつかむ場合と、硬い金属部品を扱う場合では、必要な力加減や接触面が異なるため、それぞれに適したグリッパが使われます。
以下は、ロボットハンドグリッパの主な特徴です
- 対象物に応じた多様な形状と構造
- 空気圧式・電動式・油圧式などの駆動方式
- 高精度な位置制御と力加減の調整機能
このように、ロボットハンドグリッパは単なる「つかむ道具」ではなく、高度な制御技術と設計思想が詰まった重要な要素です。
基本的な仕組みと構造
ロボットハンドグリッパは、その仕組みによって大きく3つのタイプに分類されます。それぞれの構造には特徴があり、用途によって使い分けられています。
| タイプ | 駆動方式 | 特徴 |
|---|---|---|
| 空気圧式 | エアー | 軽量・高速動作・コストが比較的安価 |
| 電動式 | モーター | 高精度制御・力加減調整が可能 |
| 油圧式 | 油圧 | 高出力・重負荷対応 |
空気圧式は軽量で高速動作が可能ですが、精密な制御には不向きです。一方で電動式はモーターによって指の開閉や力加減を細かく制御できるため、繊細な作業に適しています。油圧式は大型部品や重機器など、高トルクが必要な場面で活躍します。
なお、電動式が最も細かい力制御に向くのは事実ですが、空気圧式もセンサーと組み合わせれば精密制御が可能です。
また、多くのグリッパは「2爪型」や「3爪型」といった構造を持ち、それぞれ対象物への接触面積や保持力に違いがあります。2爪型はシンプルで高速ですが、3爪型は円筒形状など不定形物にも対応しやすいという利点があります。
このように、ロボットハンドグリッパの仕組みは非常に多様であり、用途や目的に応じて最適な選択が求められます。
ロボットハンドとの違いとは?
「ロボットハンド」と「ロボットハンドグリッパ」は混同されがちですが、それぞれ異なる役割と構造を持っています。簡単に言えば、「ロボットハンド」は人間の手全体を模した装置であり、「グリッパ」はその中でも“つかむ”機能に特化した部分です。
以下に両者の違いをまとめます
| 項目 | ロボットハンド | ロボットハンドグリッパ |
|---|---|---|
| 機能範囲 | 手全体(指・手首など) | 物体をつかむ機能のみ |
| 構造 | 多関節・多自由度 | 単純構造(2~3爪など) |
| 柔軟性 | 高い(人間の手に近い動き) | 限定的(特定用途向け) |
| 主な用途 | サービスロボット・研究開発 | 産業用ロボット・自動化ライン |
ロボットハンドは、人間の手のように複雑な動きを再現できるため、人との協働や繊細な操作が求められる場面で使用されます。一方で、産業現場ではスピードと効率が重視されるため、よりシンプルで頑丈な構造を持つグリッパが主流となっています。
つまり、「ロボットハンド=多機能」「グリッパ=専門特化」と捉えると理解しやすく、それぞれの強みを活かした使い分けが重要です。導入を検討する際も、この違いを把握しておくことで最適な選択につながります。
ロボットハンド全体の構造や導入に関する実務的な情報は、こちらのガイドで詳しく解説しています。
また、より人間の手に近い動作が可能な“5本指ロボットハンド”の構造や活用例については、こちらの記事で詳しく解説しています。
※技術的には明確な国際規格上の定義が必ずしも一貫していません。多くの技術資料では「グリッパ(gripper)」が標準用語で、「ロボットハンド(robot hand)」は研究・人型ロボット分野で用いられることが多いです。
実務では「ロボットハンド=グリッパ」として扱う現場もあります。
ロボットハンドグリッパの方式ごとの特徴|空気圧・電動・電磁式
空気圧式グリッパの特徴と構造
ロボットハンドグリッパにおいて、空気圧式は最も広く使われている方式の一つです。その理由は、構造が比較的シンプルで、軽量かつ高速な動作が可能だからです。特に製造現場では、繰り返し精度とスピードが求められるため、空気圧式の利点が活かされます。
空気圧式グリッパは、コンプレッサーから供給される圧縮空気を利用してシリンダーを駆動し、指の開閉を行います。動作が速く、軽量な部品でも確実に把持できる点が魅力です。ただし、空気源や配管が必要であり、設置スペースやメンテナンスの手間がかかるという課題もあります。
以下に空気圧式グリッパの主な特徴をまとめます。
| 特徴項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動源 | 圧縮空気(エアコンプレッサー) |
| 動作速度 | 高速 |
| 把持力調整 | 空気圧で調整可能 |
| メンテナンス性 | 定期的な配管・エア漏れチェックが必要 |
| 適用分野 | 組立ライン、小型部品の搬送など |
このように、空気圧式はスピードとコスト面で優れている一方、精密制御や静音性にはやや劣ります。用途に応じた選定が重要です。
電動式グリッパの特徴と構造
電動式グリッパは、モーターによって指を駆動する方式であり、高精度な制御が可能です。近年ではセンサーとの連携によって力加減や位置制御も細かく設定できるため、多様なワークに対応できる柔軟性があります。
この方式では、サーボモーターやステッピングモーターを使って指を開閉します。これにより、把持力や開閉速度をプログラムで細かく制御できるため、高度な自動化ラインや繊細な部品の取り扱いに適しています。また、エア源が不要なので、省スペース化にも貢献します。
電動式グリッパの主な特徴は以下の通りです。
- 精密制御が可能(位置・速度・力)
- エア配管不要で設置が簡単
- 静音性に優れる
- 初期コストは高めだがランニングコストは低い
- センサー連携によるフィードバック制御が可能
このように電動式は、高精度・高機能を求める現場に最適です。特に多品種少量生産や研究開発用途では、その柔軟性と再現性の高さが大きな強みとなります。
電磁式グリッパの特徴と構造
電磁式グリッパは、電磁石の吸着力を利用してワークを保持する方式です。金属部品など磁性体を対象とした搬送作業において非常に有効であり、シンプルな構造と高速応答性が特長です。
この方式では、通電によって磁力を発生させてワークを吸着し、通電を止めることで解放します。機械的な可動部が少ないため摩耗も少なく、メンテナンス性にも優れています。ただし、非磁性体には使用できず、吸着力もワーク形状や材質に左右されるため注意が必要です。
電磁式グリッパの主な特徴は以下の通りです。
| 特徴項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動原理 | 電磁石による吸着 |
| 対象物 | 磁性体(金属部品など) |
| 動作速度 | 非常に高速 |
| 可動部 | 少なく摩耗しづらい |
| 制限事項 | 非磁性体には使用不可 |
このように電磁式は限定的ながらも特定用途には非常に効果的です。特に金属加工ラインや自動車部品製造などでは、そのスピードと信頼性から重宝されています。
方式別比較まとめ
それぞれの方式には明確な長所と短所があります。用途や設置環境によって最適な選択肢は異なるため、それぞれの特徴を理解することが重要です。
以下に3方式の比較表を示します。
| 項目 | 空気圧式 | 電動式 | 電磁式 |
|---|---|---|---|
| 精密制御 | △(難しい) | ◎(可能) | ×(不可) |
| 動作速度 | ◎(非常に速い) | ○(速い) | ◎(非常に速い) |
| メンテナンス | △(配管管理必要) | ○(比較的容易) | ◎(可動部少ない) |
| 対象物 | 多様 | 多様 | 磁性体限定 |
| コスト | 低 | 中〜高 | 中 |
このように、それぞれの方式には一長一短があります。導入前には「何をつかむか」「どこで使うか」「どれだけ精密さが必要か」を明確にし、自社ニーズに合った方式を選定することが成功への鍵となります。
精密部品から食品まで|ロボットハンドグリッパの用途別選定
精密部品の取り扱いに適したロボットハンドグリッパの選定
精密部品の取り扱いには、繊細な操作と高い再現性が求められます。そのため、ロボットハンドグリッパの選定は非常に重要です。適切なグリッパを選ぶことで、製品の品質を保ちつつ、生産効率も向上します。
精密部品は小型で壊れやすく、わずかな力加減の違いでも破損や変形につながる可能性があります。そこで、エア圧制御が可能なソフトグリップタイプや、サーボモーター制御による高精度な動作が可能な電動グリッパが有効です。これらは力加減を細かく調整できるため、部品に過度な負荷をかけずに確実に把持できます。
以下は、精密部品向けに適したグリッパの特徴です
| グリッパタイプ | 特徴 |
|---|---|
| 電動グリッパ | 高精度制御が可能。繰り返し精度が高く、微細な調整が可能。 |
| ソフトグリップ型 | 柔軟素材で構成されており、デリケートな部品にも対応。 |
| 真空吸着式 | 接触を最小限に抑えられ、表面へのダメージを防止。 |
このように、用途に応じたグリッパを選ぶことで、製造現場でのトラブルを未然に防ぎ、生産性と品質の両立が実現できます。
食品業界で活躍するロボットハンドグリッパの特徴
食品業界では、安全性と衛生面への配慮が最優先されます。そのため、ロボットハンドグリッパには「非接触」「洗浄性」「柔軟性」といった特性が求められます。適切なグリッパを導入することで、人手不足の解消や作業効率の向上にもつながります。
食品は形状や硬さが不均一であり、従来の硬質なグリッパでは潰れてしまう恐れがあります。そのため、シリコンなど柔らかい素材で構成されたソフトグリッパや、真空吸着式の非接触タイプが多く採用されています。また、水洗いや高温殺菌に耐えられる設計も重要です。
食品業界向けグリッパの主な特徴は以下の通りです
- 柔軟素材使用:果物やパンなど形状が不安定な食品にも対応
- 衛生設計:洗浄しやすく、異物混入リスクを低減
- 非接触方式:真空吸着で直接触れずに搬送可能
これらの特性を備えたロボットハンドグリッパは、安全かつ効率的な食品加工ラインを実現します。導入によって作業者の負担軽減にもつながり、人手不足対策としても有効です。
吸着式ロボットハンドの仕組みや導入メリットについては、こちらの記事もご参照ください。
重量物・大型部品への対応力と選定ポイント
重量物や大型部品を扱う現場では、高い把持力と耐久性が求められます。適切なロボットハンドグリッパを選定することで、安全性と作業効率が大幅に向上します。
特に自動車部品や金属加工品など、大きくて重たい対象物には油圧式や強力エアチャック式のグリッパが適しています。これらは強力な把持力を持ち、高荷重にも耐えられる構造になっています。また、安全対策として落下防止機構付きのモデルも多く存在します。
重量物対応グリッパ選定時のチェックポイント
- 把持力(kgf):対象物重量より十分に高い数値か
- 耐久性:長時間稼働でも摩耗しにくい材質か
- 安全機構:停電時でも保持できるロック機能付きか
| 項目 | 推奨仕様例 |
|---|---|
| 把持方式 | 油圧式またはエアチャック式 |
| 最大把持力 | 100kgf以上(対象物に応じて調整) |
| 安全機能 | 落下防止ロック、自動復帰機能など |
このように、大型・重量物には専用設計された高出力タイプのグリッパを選ぶことが不可欠です。安全性と生産性を両立させるためにも、現場環境と対象物特性に合わせた慎重な選定が求められます。
医療・薬品分野で求められる清潔性と精密制御
医療・薬品分野では、清潔さと正確さが最も重視されます。この分野で使用されるロボットハンドグリッパには、高い衛生基準への適合と微細な制御性能が必要不可欠です。
薬剤カプセルや注射器など、小さくて壊れやすいものを扱うためには、高精度な電動式グリッパや真空吸着式が有効です。また、クリーンルーム対応設計であることも重要です。さらに、ステンレス製など腐食しづらく洗浄しやすい素材も求められます。
医療・薬品分野向けロボットハンドグリッパの要件
- クリーンルーム対応(ISOクラス5以上)
- 滅菌・洗浄対応素材(ステンレス製など)
- 微細制御可能(0.1mm単位で開閉調整)
以下は医療分野でよく使われるタイプとその特徴です
| グリッパタイプ | 特徴 |
|---|---|
| 電動マイクログリッパ | 微細操作可能。カプセルや試験管など小型対象物に最適。 |
| 真空吸着式 | 非接触搬送で衛生的。粉末薬剤容器などにも対応可能。 |
| ステンレス製チャック | 耐薬品性・耐腐食性あり。洗浄・滅菌処理にも強い。 |
このように、高度な衛生管理と精密操作が求められる医療・薬品分野では、それぞれの条件に合った専用設計のロボットハンドグリッパを導入することが成功への鍵となります。”
ロボットハンドグリッパの評価基準|把持力・速度・耐久性・コストで選定
把持力:対象物を確実に保持するための最重要要素
ロボットハンドグリッパの評価において、最も基本かつ重要な指標が「把持力」です。把持力とは、グリッパが対象物をどれだけ強く、安定して掴めるかを示す性能であり、作業の正確性と安全性に直結します。適切な把持力がなければ、対象物を落としたり、破損させたりするリスクが高まります。
たとえば、自動車部品の組立ラインでは、金属部品や重量物を扱うことが多く、高い把持力が求められます。一方で、食品や電子部品など繊細な対象物には、過剰な力を加えると破損するため、適度な把持力と繊細な制御が必要です。つまり、用途に応じた把持力の選定が不可欠です。
以下は、用途別に求められる把持力の目安です。
| 用途例 | 推奨される把持力(N) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 自動車部品 | 100~300 | 高重量対応 |
| 電子部品 | 10~30 | 精密制御が必要 |
| 食品加工 | 5~20 | 衛生面と柔軟性も考慮 |
| 一般的な搬送 | 30~100 | 汎用性重視 |
このように、把持力は単なる数値ではなく、「何を掴むか」によって最適値が異なります。導入前には必ず対象物の材質・重量・形状を確認し、それに合ったグリッパを選定することが成功への鍵となります。
速度:生産効率を左右する重要な性能指標
ロボットハンドグリッパの選定において「速度」も極めて重要です。速度とは、グリッパが開閉動作や対象物の移動をどれだけ迅速に行えるかという性能であり、生産ライン全体のスループットに大きく影響します。
たとえば、高速で稼働する包装ラインでは、一つひとつの動作時間が短縮されることで、生産量が大幅に向上します。逆に、速度が遅いとボトルネックとなり、生産効率が著しく低下します。特に多品種少量生産や短納期対応が求められる現場では、速度性能は無視できません。
以下は、用途別に求められるグリッパ速度の目安です。
| 用途例 | 推奨される開閉時間(秒) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 高速包装ライン | 0.1~0.3 | 高速応答性が必要 |
| 精密組立作業 | 0.3~0.6 | 精度重視で速度は中程度 |
| 一般搬送 | 0.5~1.0 | バランス重視 |
ただし、速度だけを追求すると制御精度や安全性が犠牲になる可能性があります。そのため、「高速かつ安定した動作」が実現できる製品を選ぶことが理想です。また、制御装置との連携によっても速度は変化するため、システム全体での最適化も忘れてはなりません。
耐久性:長期運用コストと信頼性に直結する指標
ロボットハンドグリッパは長期間使用される設備であるため、「耐久性」は非常に重要な評価基準です。耐久性とは、繰り返し使用しても性能劣化や故障が起こりにくい構造・素材・設計になっているかどうかを示します。
たとえば、自動車工場などでは1日数千回以上の開閉動作が行われるため、耐久性の低いグリッパではすぐに摩耗や故障につながります。その結果、生産ライン停止や修理コスト増加という重大な問題を引き起こしかねません。
以下は耐久性評価時に確認すべきポイントです。
- 開閉サイクル寿命(例:1,000万回以上)
- 使用素材(アルミ合金・ステンレスなど)
- 防塵・防水性能(IP規格)
- メンテナンス頻度と容易さ
これらの要素を総合的にチェックすることで、「長く使える」グリッパかどうかを判断できます。特にメンテナンス頻度が少なく済む製品は、人件費削減にもつながり、トータルコスト面でも有利です。導入時には初期費用だけでなく、「長期的な運用コスト」まで見据えた選定が求められます。
コスト:初期投資と運用費用のバランスを見極める
最後に見逃せない評価基準が「コスト」です。ロボットハンドグリッパにはさまざまな価格帯がありますが、高価だからと言って必ずしも最適とは限りません。重要なのは「価格」と「性能」のバランスです。
たとえば、高機能な電動グリッパは精密制御や多様な対象物への対応力がありますが、その分価格も高くなります。一方で空気圧式グリッパは比較的安価ですが、制御精度や柔軟性には限界があります。このように、それぞれの特徴とコスト感を理解したうえで、自社の用途や予算に合った製品を選ぶことが大切です。
なお、自社に合ったロボットハンドを選定する際には、製品ごとの特性や実績も重要な判断材料となります。ロボットハンドメーカー各社の特徴や比較ポイントについては、こちらのガイド記事をご覧ください。
以下は代表的なグリッパタイプ別のコスト比較表です。
| グリッパタイプ | 初期費用目安(円) | 特徴 |
|---|---|---|
| 空気圧式 | 30,000~100,000 | 安価・高速だが精度は劣る |
| 電動式 | 100,000~300,000 | 精密制御可能・高機能 |
| ソフトグリッパ | 150,000~400,000 | 柔軟素材対応・食品向け |
また、初期費用だけでなく「消耗部品交換」「メンテナンス」「エネルギー消費」など運用コストも考慮すべきです。特に電動式は省エネ性能にも優れており、中長期的にはコストメリットがあります。導入前にはTCO(Total Cost of Ownership)という観点から総合的に判断しましょう。
導入事例|ロボットハンドグリッパによる自動化・省人化の具体例
製造業におけるロボットハンドグリッパの導入事例
製造業では、ロボットハンドグリッパの導入が急速に進んでいます。理由は明確で、人手不足の解消と生産性向上の両立が求められているからです。特に、自動車部品や電子機器の組み立て工程では、繊細かつ反復的な作業が多く、ロボットによる自動化が非常に効果的です。
たとえば、自動車部品メーカーでは、従来は熟練工が行っていた小型部品のピッキング作業を、ロボットハンドグリッパに置き換えました。その結果、作業時間は約30%短縮され、不良率も大幅に低下しました。さらに、夜間稼働も可能となり、生産ラインの稼働率が向上しています。
以下は、製造業での導入効果をまとめた表です。
| 導入前の課題 | ロボット導入後の効果 |
|---|---|
| 作業者の疲労・ミス | 作業精度向上・不良率低下 |
| 人手不足による生産遅延 | 24時間稼働で生産性アップ |
| 熟練工への依存 | 作業標準化・教育コスト削減 |
このように、ロボットハンドグリッパは単なる機械ではなく、現場の課題を解決する「戦力」として活躍しています。今後もさらなる進化と普及が期待されます。
医療分野におけるロボットハンドグリッパの活用事例
医療現場でもロボットハンドグリッパの活用が広がっています。特に注目されているのは、薬剤ピッキングや検体搬送など、人為的ミスが許されない作業への応用です。これにより、安全性と効率性を両立することが可能になっています。
ある大学病院では、調剤室での薬剤仕分け作業にロボットハンドグリッパを導入しました。従来は薬剤師が手作業で行っていたため、ヒューマンエラーや長時間労働が問題となっていました。しかし導入後は、正確なピッキングと迅速な仕分けが実現し、薬剤師はより専門的な業務に集中できるようになりました。
医療分野での主な活用例を以下に示します。
- 調剤薬局での薬剤ピッキング
- 検体搬送や試験管の自動整理
- 手術器具の準備・洗浄工程
- 高齢者介護施設での物品配膳
これらの事例からもわかるように、ロボットハンドグリッパは医療現場においても欠かせない存在となりつつあります。人命を扱う現場だからこそ、高精度かつ安定した動作が求められ、そのニーズに応える技術として注目されています。
ロボットハンドグリッパ導入による共通メリット
製造業と医療分野という異なる現場でも共通して見られるメリットがあります。それは「省人化」「品質安定」「安全性向上」の3点です。これらはどんな現場でも重要視される要素であり、ロボットハンドグリッパはそれらを実現する強力なツールです。
以下に共通メリットを整理します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 省人化 | 人手不足への対応、人件費削減 |
| 品質安定 | 作業精度向上、不良品削減 |
| 安全性向上 | 危険作業から人を解放し、事故リスクを軽減 |
これらのメリットは一時的なものではなく、中長期的な経営改善にもつながります。特に日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、自動化技術への投資は今後ますます重要になるでしょう。
ロボットハンドグリッパは単なる機械ではなく、「働き方改革」や「現場改善」の鍵となる存在です。導入には初期コストこそかかりますが、それ以上の価値をもたらすことは、多くの事例が証明しています。
まとめ|ロボットハンドグリッパは、AI・センシング・軽量素材で用途が拡大
AIによるロボットハンドグリッパの知能化
ロボットハンドグリッパは、AI技術の進化によって飛躍的な進歩を遂げています。従来のグリッパは、決められた動作しかできず、対象物の形状や材質が変わると対応できないという課題がありました。しかし、AIを活用することで、グリッパは自ら判断し、最適な把持方法を選択できるようになっています。
たとえば、ディープラーニングを用いた画像認識技術により、グリッパはカメラで捉えた対象物の形状や位置を瞬時に解析し、それに応じた動作を実行します。これにより、不定形な物体や柔らかい素材でも安定して掴むことが可能になります。
以下はAIによって実現されている主な機能です
- 物体認識と分類
- 最適な把持点の自動選定
- 動的環境へのリアルタイム対応
- 作業履歴からの学習と改善
このように、AIによる知能化は、ロボットハンドグリッパの柔軟性と精度を大幅に向上させています。今後はさらに高度な判断力を持つグリッパが登場し、人間と同等かそれ以上の作業効率を実現することが期待されています。
センシング技術による精密な把持制御
ロボットハンドグリッパの進化には、センシング技術の高度化も欠かせません。センサーを搭載することで、グリッパは対象物の重さや硬さ、滑り具合などをリアルタイムで感知し、それに応じて力加減や動作速度を調整できます。
特に注目されているのが「触覚センサー」です。これは人間の指先のように微細な圧力変化を検知できるセンサーで、繊細な作業にも対応可能になります。たとえば、生卵や果物など壊れやすいものでも、適切な力で掴むことができます。
代表的なセンシング機能
| センサー種類 | 検知内容 | 活用例 |
|---|---|---|
| 力覚センサー | 把持力・接触圧 | 精密部品の組み立て |
| 触覚センサー | 表面状態・滑り検知 | 食品や医療器具の取り扱い |
| 近接センサー | 距離・接近検知 | 自動位置合わせ |
このようにセンシング技術は、ロボットハンドグリッパに「感じる力」を与え、人間に近い繊細な作業を可能にしています。今後はさらに高精度・高感度なセンサーが開発され、多様な産業分野で活用が広がるでしょう。
軽量素材による可搬性と省エネ性能の向上
ロボットハンドグリッパの性能向上には、素材技術も大きく貢献しています。特に軽量かつ高強度な素材の採用は、省エネ性能や可搬性の向上につながり、多くの現場で導入が進んでいます。
従来は金属製部品が主流でしたが、現在ではカーボンファイバーや高機能樹脂などが使われるようになりました。これらの素材は軽量でありながら耐久性にも優れており、高速動作にも耐えられるため、生産性向上にも寄与します。
軽量素材導入によるメリット
- ロボット全体の重量削減による消費電力低減
- 高速かつ安定した動作実現
- 可搬重量増加による作業範囲拡大
- メンテナンス頻度の低下
また、柔軟性を持つソフトマテリアルも注目されています。これにより、人との協働作業でも安全性が確保され、サービスロボットなど非工業分野への応用も進んでいます。
このように軽量素材は、ロボットハンドグリッパの設計自由度を高め、新たな用途開拓にもつながっています。今後も新素材開発とともに、その可能性はさらに広がっていくでしょう。