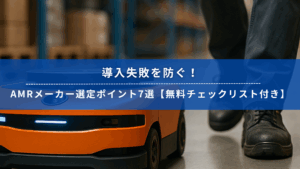「この通路幅なら、AMRは問題なく動くはず」
——そう思い込んで導入した結果、初日から動かなくなったAMRに頭を抱える。これは、現場で実際に多発しているトラブルです。
カタログスペック上は十分に見える通路幅でも、実際の現場では旋回できない、棚の角に接触する、センサーが誤作動するなど、思わぬ落とし穴が潜んでいます。
この記事では、ピッキングや工程間搬送において重要となる「狭小スペースでも使えるAMR」の選び方を、現場の視点で徹底解説します。AMR導入で失敗しないために、どこを見て、どう判断すべきか。図解やチェック表を用いながら、あなたの現場に合わせた最適な選定基準をお伝えします。
AMR導入で見落とされがちな通路幅の落とし穴とは?
カタログ値だけを信じてはいけない理由
AMR(自律走行搬送ロボット)を導入する際、多くの担当者がまず確認するのが通路幅です。製品カタログには「最小通路幅600mm」や「推奨通路幅800mm」などと記載されており、現場がそれに近い数値であれば「たぶん問題ない」と判断してしまいがちです。
しかし実際の現場では、その「たぶん」が大きなトラブルにつながることがあります。AMRは自律走行を行うため、単純な直進だけでなく、旋回や減速、障害物回避などの複雑な動きをする必要があります。そして、それぞれの動きには物理的な余白が必要です。
とくに問題となるのが、通路の「旋回スペース不足」です。たとえば、直進時には余裕のあるように見える通路でも、交差点や棚の端などで方向転換をしようとすると、AMRの本体サイズに加えて旋回半径、さらにセンサーの反応エリアや安全確保距離までもが必要になります。
現場ではこうした条件が重なり、「本来は通れるはずのルートでAMRが停止」「何度も切り返して進まざるを得ない」といった事例が多発しています。
AMR導入前の“カタログスペック信仰”は、かえって現場の柔軟な判断を妨げる要因にもなり得ます。重要なのは、数値だけを見るのではなく、「そのスペックが実際のレイアウト上でどう機能するか」を検証する視点です。
加えて、現場は日々変化します。保管物のサイズが変わる、通路に一時的な障害物が置かれる、人の通行が想定より多くなる——こうした現実の変動を前提としたAMR選定が求められます。
単なる導入成功ではなく、継続的な運用の最適化を実現するためにも、「数値だけで判断しない」という視点を常に持つことが、AMR活用の第一歩です。
「AMRの選定にあたって、さらに具体的な判断基準を知りたい」という方は、以下の記事もぜひご覧ください。
導入現場の種類別に、失敗しないためのチェックポイントをわかりやすく解説しています。
現場で求められる「小型AMR」とは?旋回半径と通行幅を正しく理解する
小型でも「動ける」とは限らない
「狭い現場だから、小型モデルを選べば問題ない」という判断も、よくある誤解のひとつです。確かに、AMR本体が小さいほど通路を通れる確率は上がりますが、それはあくまで“直進時”の話に過ぎません。
現場では、交差点での転回や、棚前での停止・後退といったさまざまな動きが必要になります。
そこで重要になるのが、旋回半径です。これは、AMRがその場で方向転換するために必要な最小限のスペースを示す指標で、モデルによって大きく異なります。
たとえば、AMRの幅が550mm、旋回半径が700mmという場合、必要な通路幅は少なくとも1,400mm以上になります。これに安全距離を加味すれば、1,600mm以上のスペースがなければ円滑な運用はできません。
この点を見落としたまま「小さいから大丈夫」と導入を決めてしまうと、AMRが旋回できずに立ち往生したり、棚に接触したりする原因になります。さらに、狭い通路で無理に旋回しようとすると、センサーが過剰に反応し、「異常停止」が頻発するケースも珍しくありません。
【旋回半径と通路幅】AMRが曲がれない理由とは?
AMRは直進できても、旋回するためには追加のスペースが必要になります。以下の図は、旋回に必要なスペースの概念を示しています。
┌───────────────┐
│ ◯────→ │ ← 直進は可能でも…
│ ↻ ↻ │ ← 旋回には追加スペースが必要
│ ◯←──── │
└───────────────┘たとえば、通路幅が600mmあり、AMR本体が550mmであっても、旋回半径が700mmの場合は物理的に回り切れません。このように、カタログ上は「通れる」サイズでも、現実には旋回できずに停止してしまうケースが多々あります。
旋回時に必要なスペースは、本体幅+旋回半径×2に加え、安全距離やセンサー検知エリアも考慮する必要があります。目安としては、旋回半径700mmの場合、少なくとも1,600mm以上の有効通路幅が必要になると考えられます。
また、現場の通路は完全に空いているわけではありません。例えば壁際に設置された非常ベルのカバーや、棚の突き出し部分、落下防止用バーなど、わずかな突起でもAMRにとっては大きな障害となります。
小型だから大丈夫——その思い込みが、大きなロスや再設計コストにつながることを、導入担当者は肝に銘じておく必要があります。機体サイズと旋回半径をセットで確認し、「小さければ通れる」ではなく「この動きがこの空間でできるか」を起点に考えることが、小型AMR導入成功の分水嶺です。
AMR導入現場に多い狭小レイアウトの実情
動線設計における“見えない制約”とは?
AMRの活用が広がる中で、現場導入時に最も見落とされやすいのが「スペースの見えない制約」です。製造業や物流倉庫では、通路幅や棚の配置が一度決まると簡単には変えられません。そのため、「既存レイアウトにAMRが対応できるかどうか」が導入の成否を左右する最初のハードルになります。
とりわけピッキング作業の現場では、AMRと作業者が同じ通路を使うため、想定外の問題が発生しがちです。作業者が棚に向かってしゃがんだり、台車を横に置いたりした瞬間、AMRの進行ルートは一瞬で塞がれます。

Factory DX
運営事務局
AMRが一時停止するだけでなく、再起動や手動回収が必要になるケースもあり、かえって工数が増えてしまうこともあるのです。
加えて、AMRには前方・側方・下部に複数のセンサーが搭載されており、これらが“安全距離”を自律的に判断します。その結果、人や障害物に近づいた際には、自動停止やルート再選択といった挙動を取るため、見た目には通れるはずのスペースでも、AMR自身が「通れない」と判断して動かなくなる現象が起きます。
こうした“見えない制約”を事前に想定するには、単にレイアウト図を見るだけでなく、実際の作業導線、棚前での人の動き、荷物の一時置きなど、現場の“癖”まで観察する必要があります。AMR導入を成功させる現場ほど、「静的なレイアウト」ではなく「動的な運用」を前提に設計しているのです。
【実効通行幅の違い】通路幅=走行幅ではない!
見た目上は通れても、AMRが実際に安全走行できるとは限りません。カタログに記載されている通路幅と、現実に必要な“実効通行幅”の違いを以下の表で確認してください。
| 項目 | 幅(mm) |
|---|---|
| カタログ上の通路幅 | 600 |
| AMR本体幅 | 550 |
| センサー反応エリア片側 | +50 |
| 実効通行幅 | 500(目安) |
AMRは安全に配慮した自律判断を行うため、センサーの検知範囲にわずかでも障害物があれば「通行不可」と認識します。たとえば、壁面のちょっとした配線カバーや段ボール箱ひとつが、AMRにとっては重大な通行障害となり得ます。
現場で多いのは、「測ってみたら通路幅600mmあったから大丈夫」という判断ですが、実際にはセンサー反応や安全距離を差し引くと、AMRが“怖がって進めない”という状態になります。これは、数値には現れない現場特有のノイズにAMRが反応している証拠です。
この“実効通行幅”の把握が不十分だと、AMRが頻繁に立ち止まり、業務が止まるばかりか、人手による回収や対応が発生し、本末転倒の結果になります。数値的な余白をどれだけ確保するかが、AMR運用の安定性を左右するのです。
AMR選定の前に必ず確認すべき4つのポイント
1. 最小通路幅と旋回半径の見方
AMR選定で最初に理解すべきなのは、「最小通路幅」と「旋回半径」という2つの異なる概念です。
最小通路幅は、AMRがまっすぐ進むために必要な幅を指します。一方、旋回半径は、方向転換や回転動作をする際に必要なスペースです。この2つを混同して「600mmの通路があるからOK」と考えると、カーブやT字路で動けなくなるリスクがあります。
たとえば、旋回半径が700mmのAMRを通路幅1,000mmの現場に入れた場合、AMRは通路内で回転することができません。直進は可能でも、方向転換が必要な場面では手詰まりとなります。
AMR選定の際に見落とされがちな全体的なポイントについては、こちらの記事も参考になります。
【簡易計算式】旋回に必要な通路幅の求め方
以下の簡易式を使えば、自社通路でAMRが旋回できるかを予測できます。
必要通路幅(mm)= 旋回半径 × 2 + 安全距離(両側100mm)
例:旋回半径700mm → 700×2+200=1,600mm旋回動作が発生する区画にこの幅が確保できていない場合、導入モデルの見直しや、レイアウト調整が必要になります。
2. 搬送方式ごとの制約
AMRの搬送方式には、積載型、牽引型、リフト型といったバリエーションがありますが、それぞれ走行条件やサイズ制約に違いがあります。
たとえば牽引型は、荷物をトレーラーで引くため、AMR本体よりも全長が長くなります。その分、旋回時に大きなスペースが必要で、狭い通路では取り回しが難しくなります。逆に積載型は、小回りが利くため、ピッキングエリアのような限定空間に向いています。
【搬送方式別比較表】AMRタイプによる制約の違い
| 搬送方式 | 特徴 | サイズ制約 | 旋回性 | 適した用途 |
|---|---|---|---|---|
| 積載型 | 本体に荷物を載せる | 小〜中 | 高 | ピッキング、小型部品搬送 |
| 牽引型 | トレーラーを牽引 | 中〜大(全長大) | 低(長さ影響) | パレット搬送、長距離搬送 |
| リフト型 | 荷物を持ち上げて運搬 | 中(高さ制約あり) | 中 | 工程間搬送、自動棚受け渡し |
現場ごとのスペース・業務内容に応じて、方式を使い分けることが、AMR活用の最適化につながります。
3. 周辺機器や棚との干渉リスク
AMRの選定では、本体サイズだけでなく、突起物の有無やセンサーの位置なども確認が必要です。とくにリフト型や多段式のAMRでは、センサーやアームが本体よりも外側に張り出しているケースがあります。
現場で起こりやすいのは、AMRが棚の角や床の段差に引っかかって停止するパターンです。とくに棚のエンドキャップや補強バーなどは、設計図には載っていないものも多く、干渉リスクを軽視しがちです。
【干渉リスク図解】棚やエンドキャップに引っかかる理由
┌────────────┐
│ 棚 ▓ ←AMRセンサー部が接触
│ AMR→▓
│ 棚 ▓
└────────────┘現場での実機テストや3Dシミュレーションを行い、「動線上に何があるか」を可視化しておくことがトラブル回避につながります。
4. ピッキング時の人との共存
ピッキング現場では、人とAMRが常にすれ違う環境が前提となります。通路幅が確保されていても、作業中の人が棚の前に滞在している場合や、手押し台車を一時的に通路脇に置く場合など、AMRの進路が物理的・動的にふさがれる状況は日常茶飯事です。
このような環境下でのAMR導入には、センサーの性能、減速/停止制御の精度、人感検知への対応力など、ハードとソフト両面での調整が求められます。
【ピッキング動線図解】人とAMRが共存する通路
┌────────────┐
│ 作業者 ← 棚 → AMR │
│ 通路(800mm) │
└────────────┘見た目には800mmあっても、作業者がいることで通行不可となる場面は多くあります。人とAMRの“衝突しないための動線”をあらかじめ設計し、必要であれば“片側通行ルール”や“停止タイミングの調整”をプログラミングに組み込むことで、スムーズな共存が実現します。
ケース別に見るAMR選定基準と判断ポイント
AMRを選定する際に重要なのは、製品スペックをただ一覧で比較することではありません。現場での「使われ方」に応じた適性を見極めることが、本当の意味での最適化につながります。とくにピッキングと工程間搬送は、AMRに求められる要件が大きく異なるため、導入前に“目的別に見る視点”を持つことが不可欠です。
ピッキング作業に適したAMRの条件とは?
ピッキング現場では、作業者が常時棚と通路の間を移動しており、人とロボットが頻繁に交錯するのが特徴です。このような環境では、AMRの性能が高いだけでなく、人との協調性や安全性が十分に担保されているかが問われます。
以下のようなスペックが重要となります。
- 障害物回避性能
作業者やカートなどが頻繁に通る通路では、高精度な障害物回避機能が必須です。センサーの死角が少なく、移動体に対して柔軟に減速・停止できることが求められます。 - 停止位置の正確性(±10mm程度)
棚前での荷物の受け渡しやピックアップ動作において、数センチのズレが作業効率に直結します。停止精度が高ければ、人が毎回位置を調整する必要がなくなり、作業ストレスの軽減にもつながります。 - 人感センサーや音声アラート
物理的な安全確保だけでなく、「人に気づかせる」仕組みも重要です。音声による接近通知や点灯による存在アピールは、混雑した現場での接触事故を防止するために効果的です。
実際、ピッキングに適したAMRモデルは、自動停止距離が短く、棚間の狭い通路でもスムーズに動けるよう調整されたものが多くあります。

Factory DX
運営事務局
製品選定時には、「どのように動くか」ではなく、「どのような人の動きと重なるか」に注目するのがポイントです。
工程間搬送で見落とされがちな制約
工程間搬送は、一見すると「単純な往復搬送だから簡単」と捉えられがちですが、実は非常に多くの見落としポイントがあります。特に注意すべきなのは、ルート上の「旋回」と「Uターン」、そして「搬送物との干渉」です。
- 分岐点での旋回性
分岐点や交差点では、搬送中のAMRがスムーズに方向転換できなければ、滞留や渋滞が発生します。旋回半径が大きいAMRを使ってしまうと、交差点内での切り返しが頻発し、バッテリー消費や部品の劣化を早める要因になります。 - Uターン可能な幅
作業エリアの端でUターンを必要とする工程では、スペースが不足すると回り切れず、AMRが何度も切り返すことになります。これにより搬送時間が増加し、全体のサイクルタイムが延びてしまいます。 - 周辺設備との接触リスク
工場内には、ベルトコンベアや架台、棚、工具置き場など、固定物が多く存在します。牽引型や背高型のAMRは、これらに接触するリスクが高いため、搬送物のサイズと合わせて「通過クリアランス」が確保されているかを必ず確認しましょう。
工程間搬送の安定性は、定時出荷やライン稼働に直結するため、一度でもAMRが止まると全体のスループットに影響を与えます。繰り返し運用に耐え得るモデルとレイアウト設計が不可欠です。
【AMR用途別適性マトリクス】通路幅や安全性から選ぶ
以下の表は、用途別にAMRの適性を簡潔にまとめたものです。自社の利用シーンと照らし合わせながら、導入可否の初期判断に活用してください。
| 用途 | 通路幅が狭い | 棚間距離が短い | 周囲に人が多い | 旋回が多い | 推奨レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| ピッキング | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 非常に適している |
| 工程間搬送 | ◯ | △ | ◎ | △ | 条件付きで可能 |
このマトリクスはあくまで一般的な傾向を示したものですが、実際にはAMRの設計思想やカスタマイズ可能性によって、運用可能な範囲は広がることもあります。重要なのは、「この用途だからこの機種」と機械的に選ぶのではなく、「この現場の制約と用途をどうバランスさせるか」という視点を持つことです。
まとめ:AMR導入は「現場目線」の事前設計が成功の鍵
AMRの導入成功は、製品の性能だけで決まるものではありません。むしろ、導入前にどれだけ現場の制約を把握し、AMRの特性と丁寧に照合できるかが、長期的な安定稼働の分かれ道になります。
よくある失敗例は、「このモデルが人気らしい」「これが小型でよさそう」といったカタログ主導の選定です。しかし、現場には独自の制約があり、他社で成功したモデルがそのままフィットするとは限りません。
以下の3ステップを徹底することで、見落としのない、再現性の高いAMR導入を実現できます。
【導入成功の3ステップ(図解)】失敗しないAMR導入3ステップ
STEP1|現場条件の把握
└ 通路幅・棚間・レイアウトなど物理制約を確認
↓
STEP2|AMRスペックとの照合
└ サイズ・旋回半径・停止精度・搬送方式を検討
↓
STEP3|試験走行で確認
└ 仮レイアウトで干渉やセンサー誤作動の有無をチェック最終的に重要なのは、「このモデルが使えるか」ではなく「この現場でどう使うか」を起点に判断することです。現場に合ったAMRを見極め、トラブルのない安定運用を手に入れるためには、この3ステップこそが最短ルートなのです。