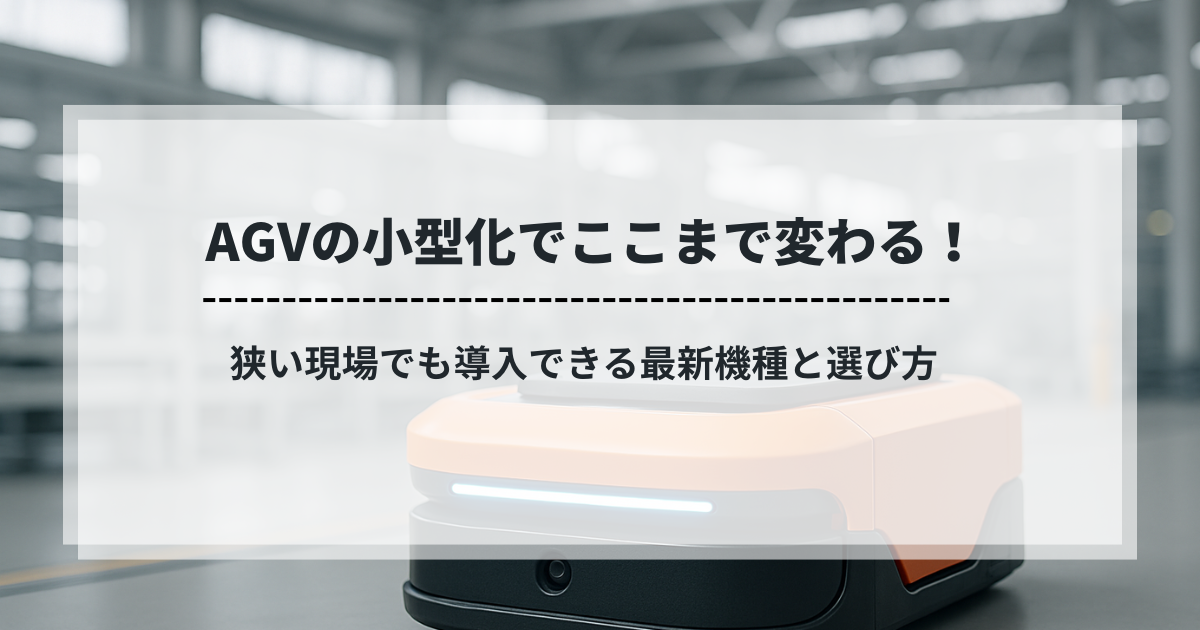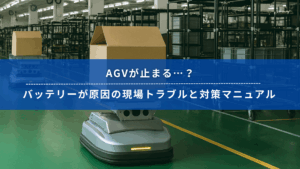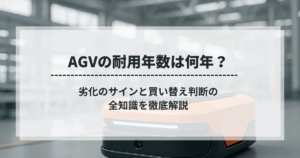近年、多くの製造業・物流業では、自動搬送ロボット、すなわちAGV(Automatic Guided Vehicle)の導入が進んでいます。人手不足、業務効率化、安全性向上といった理由からAGVは不可欠な存在となりつつあります。
しかし、「通路が狭くてAGVが使えない」「レイアウト変更ができない」「設備の下を通過させたい」といった声も少なくありません。従来の大型AGVでは対応できない現場課題に直面している担当者は多く存在します。
そこで注目されているのが「小型AGV」および「超小型AGV」です。これらの製品は、限られたスペースや特殊な環境でも柔軟に対応でき、従来のAGVが導入困難だった現場にもソリューションを提供します。
この記事では、AGV導入を検討するすべての現場担当者に向けて、小型・超小型AGVの特長、製品比較、選定ポイント、導入メリットなどを徹底解説します。さらに、図表や診断チャートを交えながら、自社の現場に最適なAGVを選ぶための具体的なノウハウを提供します。
なぜ今、小型AGVが選ばれるのか?導入が進む背景とその理由
小型AGVの定義と基本性能
AGV(Automatic Guided Vehicle)とは、無人であらかじめ設定されたルートを自律的に走行し、部品や資材などを搬送するロボットです。中でも「小型AGV」とは、一般的に本体幅が500〜700mm前後の比較的コンパクトなタイプを指し、工場や物流施設における狭小エリアや制限された通路での搬送業務に特化しています。
一般的な搬送対象は10〜500kg程度の中軽量物であり、移動距離は構内の短〜中距離(10〜200m)に設定されることが多く、主にライン間搬送や部品ピッキングなどの反復作業の自動化に活用されます。
走行方式には以下のようなバリエーションがあります。
- 磁気誘導式:床に貼られた磁気テープをセンサーで読み取る方式。低コストだが柔軟性に欠ける。
- QRコード誘導式:床面のマーカーを読み取り位置補正しながら走行。比較的自由度が高い。
- SLAM方式:環境マップを自動生成し、自律走行を実現。高精度で導入柔軟性が高い。
- レーザー誘導式:反射板やLiDARを使いミリ単位の制御が可能。長距離搬送に向いている。
特にSLAM方式を採用したモデルは、狭小エリアや頻繁なレイアウト変更に対応しやすく、工場内物流の柔軟性を飛躍的に高めています。
小型AGVのサイズ感と対応現場マトリクス
以下、小型AGVがどのような通路幅・レイアウトに適合するかを、表としてまとめました。
| 通路幅 | 適合モデル例 | 主な用途 | 対応現場 |
|---|---|---|---|
| ~550mm | 超小型AGV | 軽量物搬送、ラボ・医療向け | 研究施設、病院、クリーンルームなど |
| 550〜700mm | 小型AGV(低床) | 狭小通路搬送、設備下搬送 | 食品工場、小型倉庫、生産現場 |
| 700〜900mm | 標準小型AGV | 部品搬送、ライン間移動 | 一般製造業、電子機器組立ラインなど |
| 900mm以上 | 中型以上AGV | 重量物搬送、パレット搬送 | 物流センター、自動車工場など |
【補足解説】
通路幅700mm未満に対応できるかどうかが、一般的なAGVと小型・超小型AGVの分岐点になります。
とくにレイアウト制限が厳しい現場では「旋回半径」「最小通路幅」などのスペック確認が必須です。表を参考に、自社の物理条件を整理した上で選定を進めましょう。
なぜ「小型化」が進んでいるのか?
少子高齢化や労働人口の減少により、製造・物流の現場では省人化・自動化のニーズが急速に高まっています。その中でAGVの導入が注目されていますが、現場には「思ったより通路が狭くて使えない」「他の設備との干渉で運用が難しい」といった、サイズに起因する導入障壁が少なくありません。
ここで「小型AGV」が脚光を浴びているのは、単にサイズが小さいという理由だけではありません。スペース効率・レイアウト柔軟性・安全性という三要素を同時に満たせる「最小リスクの自動化装置」として、多くの中小現場で評価されているからです。
小型AGV導入の背後にある要因を3つの層に分け、単なる自動化ニーズではない「現場のリアルな課題」を以下の表にまとめました。
| 要因階層 | 具体的な背景課題 | 小型AGVが解決できる理由 |
|---|---|---|
| 社会的要因 | 労働人口の減少、人件費高騰、安全性強化 | 無人搬送により人員負担を軽減、安全運用が可能 |
| 現場制約 | 通路幅が狭い、既存設備と干渉、床に段差や制限がある | コンパクトな車体でレイアウト変更不要、低床対応も可能 |
| 管理課題 | 反復作業に人員を割けない、ミスが許されない、作業属人化の回避 | 繰り返し作業を自動化し、標準化・ミス低減を実現 |
【補足解説】
小型AGVは単なる「スモールモデル」ではなく、「現場の制約を乗り越える実務的ツール」としての価値があります。導入の背景には、人手不足だけでなく、「大がかりなレイアウト変更をせずに済む」「属人化した作業を標準化できる」といった現場運用上のリアルなメリットが存在します。
なぜ中小企業に最適?小型AGVは“失敗しづらい”自動化の第一歩
意外と知られていないのが、「小型AGVは導入における初期投資と失敗リスクが比較的低い」という事実です。中型・大型AGVは導入に数千万円単位のコストがかかり、レイアウトの大規模改修も必要となるケースが多く、初期判断を誤れば大きな損失を招きます。
一方、小型AGVは以下の理由で「トライアルしやすく、改善型導入に向いている」という特性があります。
つまり、「スモールスタートでスケーラブルな自動化」が可能な選択肢として、設備導入に慎重な中堅・中小企業において成功率が高いのです。
このように、小型AGVはただサイズが小さいだけでなく、導入ハードルが低く、現場の実情に合致した「最も成功しやすいAGV導入モデル」と言えます。
導入を検討する際には、自社の現場規模や運用課題に応じて、小型AGVの特性を活かした段階的な導入戦略を立てることが重要です。
なお、AGVやAMRを取り巻く市場全体の成長トレンドや、ナビゲーション技術・AI制御の進化などについては、以下の記事でより詳しく解説しています。自社の中長期的な設備投資を見据える上でも、併せてご覧ください。
小型か超小型か?AGV導入で失敗しないための違いと選び方
搬送スペースに合わせた選定が導入成功を左右する
AGV導入の最大の落とし穴は、「小型であれば通れるだろう」と安易に判断してしまうことです。現場ごとに通路の幅、交差点の角度、設備との間隔、人の往来の頻度などが大きく異なるため、AGVのサイズや性能が現場と合致しないと、思ったように走らない、もしくは搬送ルートそのものが成立しないというケースも少なくありません。
そのため、まず押さえるべきは「小型」と「超小型」の明確な違いです。両者は単にサイズが違うだけでなく、用途、性能、導入先の前提条件までもが異なります。
小型と超小型AGVのサイズ・用途・対応現場比較
どちらのAGVが自社の現場に適しているかを判断しやすいよう、サイズ、最小通路幅、用途、使用環境の違いを整理しました。
| 分類 | 本体幅の目安 | 最小通路幅 | 主な用途 | 対応環境例 |
|---|---|---|---|---|
| 小型AGV | 500〜700mm | 700〜900mm | 工程間搬送、ライン供給、軽中量物の自動搬送 | 製造業(組立工場、部品加工)、物流センター、自動車工場 |
| 超小型AGV | 240〜500mm | 500〜700mm | 狭小スペースでの搬送、設備下潜行、ピッキング補助など | 医療施設、研究施設、クリーンルーム、電子機器製造、食品工場など |
【補足説明】
特に重要なのが最小通路幅の確認です。
カタログ上で「幅500mm」と記載されていても、実際の旋回や停止動作には+100〜200mmの余裕が必要です。
床に固定設備がある場合や通行者とすれ違う可能性がある場所では、さらに広めの設計が求められます。超小型AGVはこうした狭所に特化した構造を持っており、SLAMやミリ波センサーなどを駆使した高精度制御でその強みを発揮します。
活躍する現場の違いは「空間」と「運用スタイル」にあり
AGVの適性を決めるのは、広さだけではありません。どのような搬送物を、どのような環境で、どのくらいの頻度で運ぶのか。この運用スタイルの違いが、選ぶべきAGVタイプを決定づけます。
超小型AGVは、たとえば以下のような制約を持つ現場で導入されています。
- 既存の人手による搬送ルートをそのまま活かしたい
- 通路幅が550mmしかないが、そこを毎日往復搬送したい
- 設備の下を通過して反対側のラインに回りたい
一方、小型AGVは以下のような現場で多く使われています。
- 生産ライン間の距離が長く、複数種類の部品を定期的に移動させる
- 棚や架台を回避しながら安定して走行させたい
- 工程ごとに搬送頻度が異なるため、柔軟なルート設定を行いたい

Factory DX
運営事務局
見落としていたスペースこそ、自動化のチャンスかもしれません。
使用環境別AGV選定マトリクス
現場の用途と物理環境に応じて、どちらのAGVが最適かを判断しやすくするため、環境別のAGVタイプマトリクスを以下に示します。
| 使用環境 | 運用の特徴 | 最適なAGVタイプ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医療・研究施設 | 通路が狭く、人との共存が必要、静音性必須 | 超小型AGV | SLAM制御+低速走行モデルが安全運用に最適 |
| クリーンルーム | 粉塵厳禁、導線の確保が困難 | 超小型AGV | 密閉構造+リフトレス構造が求められる |
| 食品工場 | トレイ搬送、段差・傾斜のあるレイアウト | 小型AGV | 防水・滑り止めタイヤ付きモデルが有効 |
| 中小製造工場 | 部品の工程間搬送、狭い交差点あり | 小型AGV | 90度旋回対応+狭角交差通行モデルが推奨される |
| ピッキング・搬送支援エリア | 搬送物が軽量かつ多品種、定期往復が多い | 超小型AGV | AI搭載モデルで搬送ルートを自己最適化可能 |
【補足説明】
表を見れば明らかなように、超小型AGVは「人がやっていた搬送業務」をそのまま置き換えるようなケースで活躍します。一方、小型AGVは「工程の一部を安定して任せる装置」として、より継続的・量的な搬送に向いています。選定基準は、“置き換える業務の種類”と“現場の障害物条件”で決めるのが鉄則です。
導入前に知っておくべき「見落としがちな差」
実機サイズだけで判断してしまうと、設置後に思わぬ問題が発生することがあります。以下は、AGVの導入相談時に頻出する“見落とされがちなポイント”です。
このような問題を防ぐには、「仕様書のサイズ+最低200mmの安全マージン」で検討することが推奨されます。
また、現場の実寸を正確に測定し、事前にトライアル搬送を行うことも非常に有効です。
ここでしか使えない!超小型AGVが真価を発揮する現場とは?
数十センチの空間すら「搬送路」に変える技術革新
従来、通路幅600mm未満の現場では、人が押す台車ですらすれ違いが困難であり、AGV導入は“現実的ではない”とされてきました。ところが、幅240mm程度の超小型AGVの登場によって、この常識が完全に覆されています。
たとえば、医療施設のナースステーション周辺、ラボ内のサンプル搬送通路、クリーンルームでの無菌物資の移動など、非常に限られたスペースでも、センサーとSLAM技術による高精度な自律走行が実現され、無人搬送が可能になっています。
このセクションでは、どのような環境で超小型AGVが実際に活用されているのかを、具体的な現場条件ごとに整理します。
超小型AGVが導入されている現場例と主な役割
導入現場別に、AGVの用途と最適なモデルを整理した一覧表です。自社の職場や施設と照らし合わせながらご覧ください。
| 使用現場 | AGVの主な役割 | 特に有効な機種タイプ |
|---|---|---|
| 医療施設(病棟・薬局) | 薬剤・医療機器・消耗品の無人搬送 | 超小型AGV(SLAM搭載) |
| 食品加工工場 | 小型トレイの搬送、検品ラインへの供給 | 小型AGV(低床設計) |
| 研究ラボ・大学施設 | 試薬・分析物・サンプルの定期搬送 | 超小型AGV(静音・耐薬品設計) |
| クリーンルーム | 無菌物の自動搬送、接触レスの搬送補助 | 超小型AGV(密閉構造・低発塵) |
| 精密機器工場 | 電子部品・基板のピンポイント搬送 | 超小型AGV(最小旋回対応) |
【補足説明】
表に挙げたような現場では、AGVに求められるのは「運ぶ力」ではなく、「通れること」「止まれること」「人の動線を邪魔しないこと」です。超小型AGVはその条件を満たす唯一の選択肢であり、搬送の“無人化率”を上げるための起点として使われることも少なくありません。
台車搬送の“代替”から“上位互換”へ
多くの施設では、軽量物の搬送は台車での手動作業が当たり前になっています。しかし、その作業は実際には多くの人手を取られ、疲労や属人化の原因にもなっています。
超小型AGVは、その台車作業を「同じスペースで」「人と同じ動きで」「自動で」実現できるという意味で、単なる代替ではなく機能的な上位互換となり得ます。
特に次のような作業がある場合、超小型AGVは即戦力になります。
- 食品トレイを冷蔵庫から作業ラインへ数分ごとに搬送する
- 検体を採取から分析室まで決まったルートで往復搬送する
- ラボで朝昼夕に一定ルートで機器用バッチを運ぶ
- 病院で使用済み器具を自動で回収・搬送する
これらの業務は、いずれも「軽量・定型・高頻度」という特徴があり、AGVによる置き換えによって人員がより専門性の高い業務に集中できるようになります。
「無理だ」と思った現場こそ試すべき!動線可視化でAGVの新ルート発見
「うちの現場は狭すぎて無理だろう」と思われている方こそ、動線マッピングを試してみてください。
超小型AGVは、わずか550mmの通路幅でも旋回・停止が可能で、棚と棚の隙間や機器の下など“これまでは搬送に使えなかったスペース”をルートに変えられる可能性があります。
施設図面に以下のような点を記入するだけで、AGV化のポテンシャルを客観的に把握できます。
- 人の往来が多い区間
- 頻繁にモノを運ぶ距離とルート
- 台車の通行幅
- 障害物や段差の位置
- 暗所・狭所・清潔エリアの有無
このプロセスを踏めば、「思っていたより搬送できる区間が多い」「意外とAGVで代替可能」という発見につながることが多くあります。

Factory DX
運営事務局
“狭いから無理”は思い込み。
動線を見直せば、意外な抜け道が見つかることが多いです。
AGV導入における失敗の多くは、選定段階での見落としが原因です。
導入目的別の比較軸や、確認すべき機能を整理したガイドを作成しました。
検討初期だからこそ、正しい比較軸を今のうちに押さえておきませんか?
→ AGV比較ガイドを今すぐダウンロード
もう迷わない!小型・超小型AGVの選び方5つの鉄則とは?
AGV選びは単なる「サイズの比較」では成立しません。現場の制約条件、運用スタイル、搬送対象の特性、将来的な拡張性までを見据えて選定しなければ、たとえ導入しても「思ったように使えない」「通路に収まらない」「メンテナンスが煩雑」など、継続的な運用障害を生むリスクがあります。
このセクションでは、AGV選定時に絶対に押さえておくべき5つのポイントを、実際の比較データと診断チャートを交えながら整理します。
① 搬送物の重量とサイズ
AGVが搬送する物の大きさと重さは、選定の最も基本的な判断軸です。
- 30kg以下の軽量物:超小型AGVで十分対応可能。医療・研究用途などに多い。
- 100kg〜1,000kgの中重量物:小型〜中型AGVを選定。工場内部品搬送やパレット対応向け。
ただし、重量に加えて“搬送対象のサイズ(幅・長さ・高さ)”が本体サイズとアンバランスな場合は、安定性や重心のブレが問題になるため、必ず搭載可能寸法も確認が必要です。
② 対応通路幅・最小回転半径
実際の導入現場では、「搬送中にすれ違えるか」「交差点を曲がれるか」が可否を決めます。
通路幅とAGV本体の関係性を直感的に理解できるよう、サイズ区分ごとに必要な通路幅の目安を表にまとめました。
| AGVサイズ区分 | 本体幅の目安 | 推奨通路幅の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 超小型 | 240〜500mm | 550〜700mm | SLAM搭載モデルで精密走行可能 |
| 小型 | 500〜700mm | 700〜900mm | 区画・誘導ライン設計が前提 |
| 中型 | 800〜1,000mm | 1,000〜1,200mm | 屋内重量物対応モデル |
| 大型 | 1,000mm以上 | 1,200mm以上 | パレット/屋外対応 |
【補足説明】
旋回半径も通路幅と同様に重要なチェックポイントです。小型AGVでも最低900mm以上の回転幅を必要とするモデルもあるため、「一方通行でしか走れない」「途中で向きを変えられない」といった運用制限が生じないよう、必ず事前にシミュレーションすることを推奨します。
③ センサー・ナビゲーション方式
ナビゲーションの方式は、搬送ルートの自由度とメンテナンス負荷を大きく左右します。
各方式の特徴と使い分けを、導入コストと柔軟性の観点から整理しました。
| ナビゲーション方式 | 特徴 | 主な用途・メリット |
|---|---|---|
| 磁気テープ誘導 | 導入が簡単/コスト低/レイアウト固定 | 単一ルートの定期搬送に最適 |
| QRマーカー誘導 | レイアウト変更に柔軟/中精度対応 | 倉庫などでの中距離搬送に多く採用 |
| SLAM方式 | 自己位置推定/高精度走行/障害物回避可能 | 通路の混雑・障害物の多い現場に最適 |
| レーザー誘導 | リフレクターによる高精度誘導/長距離対応 | 中大型AGVや広範囲施設での安定搬送に有効 |
【補足説明】
ナビゲーション方式は、後からの切り替えが困難な構造部です。通路や設備変更が多い現場では、初期費用が高くてもSLAM方式を選ぶことでトータルコストが安くなる場合が多くあります。初期投資より「運用の柔軟性」を優先する姿勢が、失敗しない導入の鍵です。
④ 稼働時間・充電方式
多くの現場では「1日8時間稼働できれば十分」とされますが、次の2点は軽視できません。
- 中間充電の有無:昼休憩やアイドル時間を活用できるか
- 自動充電対応か:充電ドッキングステーションの有無
近年では「任意地点で自動ドッキング→充電→自律復帰」まで可能なモデルが主流化しており、これにより人手を介さず24時間体制での無人運用が可能になります。
AGVのバッテリーに関する種類や寿命、選定ポイントについては、こちらのガイドで詳しく紹介しています。
⑤ 導入環境の特殊要件
最後に見落とされがちなポイントが、AGVの対応環境です。
- 段差・傾斜があるか:車高・タイヤ径・駆動方式に依存
- 湿度・温度変化があるか:防塵・防滴・耐冷耐熱設計が必要
- 清浄度や静音要件:医療・食品現場では排気・音も重要指標
こうした要素を確認せずに選定すると、「設備の下をくぐれない」「斜面を登れない」「クリーンルーム基準を満たさない」といった後戻りのできないミスマッチが起きます。
AGV選定フロー図:現場に最適な機種の見つけ方
現場条件に基づいて、どのタイプのAGVがフィットするかを簡易的に判断できる選定チャートです。
| 質問 | Yes → | No → |
|---|---|---|
| 搬送物は100kgを超えますか? | 中型または大型AGVを検討 | 超小型または小型AGVを検討 |
| 通路幅は600mm未満ですか? | 超小型AGVに絞り込み | 小型AGVで対応可能 |
| 段差や傾斜がある場所で使用しますか? | 四輪駆動・車高調整タイプを検討 | 標準モデルで十分対応可能 |
| SLAMによる自律走行が必要ですか? | SLAM搭載モデルを優先選定 | 磁気テープ誘導モデルでも対応可能性あり |
【補足説明】
このチャートはあくまで初期選定の指針であり、詳細な導入可否は現場ヒアリングや実地検証が不可欠です。特に超小型AGVは「スペックより現場設計とのマッチング」が成否を分けるため、必ず現場環境の把握→マッチング→試走トライアルの3ステップを確保することを推奨します。
どれを選ぶ?国内メーカー製の小型・超小型AGVスペック比較一覧
小型・超小型AGVの導入に際しては、「どの製品が自社の環境に合うか?」という初期選定が重要です。現場条件や搬送ニーズが細かく異なる中で、単純に「一番小さい」「一番安い」だけでは判断を誤る可能性があります。以下の表は、国内で導入可能な代表的なモデルを、サイズ・搬送能力・特徴とともにまとめたものです。
この比較をもとに、自社の現場と照らし合わせて最適な選定にお役立てください。
小型・超小型AGVの主要製品比較表【国内メーカー】
| ベンダー | 製品名 ・型番 | 幅 × 奥行 × 高さ (mm) | 搬送 能力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヘッズ | HRVT-M350 | 幅450 × 奥行1550 × 高195 | ~450kg | 幅450mmで狭通路対応、全長長め。超低床設計で設備下通過が可能。スピンターン対応。 |
| ASPINA(シナノケンシ) | Aspina AMR | 幅600 × 奥行600 × 高600 | ~100kg | 600mm角の自律搬送ロボット。物流拠点や研究施設に最適。800mm通路で運用可。 |
| Preferred Robotics | Kachaka Pro | 幅240 × 奥行387 × 高124 | ~30kg | 幅240mmの超小型。SLAM搭載、自動充電対応。家庭・施設内搬送にも対応。 |
【補足説明】
それぞれのAGVには明確な得意分野があります。たとえば、HRVT-M350は「設備下の潜行」や「通路幅500mm未満」などの特殊環境向け。一方で、Kachaka Proは家庭や医療施設のような“人と共存する狭小空間”において、非接触・静音搬送が求められる現場で活躍します。

Factory DX
運営事務局
AGV選定は“どれも同じ”に見えますが、実は“適材適所”がハッキリ分かれます。
この比較を活用し、「どの製品なら実現できるか」「現場の制約をカバーできるか」を基準に選定を進めることが、失敗しない導入への第一歩です。
なお、AGVメーカーのシェアや信頼性、選び方のポイントについては、こちらの比較記事をご覧ください。
現場が語る!小型AGVで実現した自動化とコスト削減の成果
小型AGVの導入は、単なる人手不足の解消にとどまりません。運用フロー全体の最適化によって、コスト削減、ミス低減、搬送の安定性向上、従業員の負担軽減など、多面的な業務改善を実現する手段として注目されています。
ここでは、実際にAGVを導入した現場の「導入前後の違い」と「その定量効果」を可視化し、AGVがどれほど現場に貢献するかを具体的に紹介します。
Before/After比較:AGV導入による業務改善効果
以下は、従来は人手によって手押し台車で行っていた搬送作業を、幅600mm未満の小型AGVに置き換えた中小製造業の実例に基づいた定量比較表です。
| 項目 | 導入前(手作業) | 導入後(小型AGV) |
|---|---|---|
| 搬送人数 | 2名/回 | 0名(完全自動) |
| 搬送時間 | 7分/1往復 | 3分/1往復 |
| 搬送頻度 | 6往復/1時間 | 12往復/1時間 |
| 年間コスト削減額(概算) | 約180万円(人件費換算) | 約20万円(電気代・保守費用) |
【補足説明】
この事例では、搬送対象は15〜20kg程度の部品箱で、往復距離は約50メートル。従来は2名体制で台車搬送していましたが、AGV導入により完全自動化され、作業者はその時間を他の生産業務に再配分できるようになりました。結果として生産性が15%向上、残業時間も大幅に削減されました。
このように、「たった1台のAGVでも、現場のボトルネック解消に直結する」ことが多くの現場で実証されています。特に、小規模工場や単品少量生産を行う製造ラインでは、小型AGVによる省人化=全体効率の底上げに繋がることが多く、導入効果が非常に高く評価されています。
小型AGVの導入費用はいくら?ROIと費用対効果を徹底解説
AGVを導入したいと考える担当者にとって、費用対効果が見えなければ社内稟議を通すことは困難です。ここでは、国内での一般的な小型AGVの導入コストと、その費用をどの程度の期間で回収できるのかをシミュレーション形式で明示します。
この数値をもとに、自社の業務量や人件費と照らし合わせて、「導入すべきタイミングかどうか」の判断材料にしてください。
導入費用と回収期間シミュレーション
以下は、一般的な小型AGV(積載100〜500kg、SLAM対応)の導入を想定した費用とROIの試算例です。
| 項目 | 小型AGVモデル例 |
|---|---|
| 初期費用 | 約250〜350万円 |
| 年間保守費用 | 約10〜15万円 |
| 月間電気代 | 約1,000円前後 |
| 年間労務コスト削減額(概算) | 約180万円(人件費1名分に相当) |
| ROI回収期間 | 約1.5〜2年で回収可能 |
【補足説明】
この試算では、1日8往復×20日稼働を前提に、「従来1名の作業員が手動搬送していた業務」をAGV1台が代替したケースを想定しています。機種によっては初期費用をさらに抑えられる低価格モデルや、リース・サブスク型で月額数万円から利用できる選択肢もあります。
なお、AGVが実際にどれくらい使えるのか、寿命や劣化のサインについてはこちらの記事をご覧ください。
また、ROIは単なるコスト削減だけでなく、「現場の省力化」「人的エラーの減少」「生産性の安定化」といった目に見えづらい業務メリットも含めて評価する必要があります。
結果的に、月々のランニングコストが極めて低いため、長期的に見るとAGVの導入は人件費に比べて非常に高い費用対効果が得られる設備投資と言えます。

Factory DX
運営事務局
労務コストが減るだけでなく、ヒューマンエラーまで減らせるとしたら?初期費用300万は“リスクではなく、未来への種まき”だと考えてみてください。
迷ったらここをチェック!小型AGVに関するよくある質問10選
- 最小の通路幅で走行できるAGVはありますか?
はい。幅240mmの超小型AGV「Kachaka Pro」などは、550mm前後の通路でも走行可能です。通路幅600mm以下でも導入できる機種は複数あります。
- 小型AGVでも段差や傾斜に対応できますか?
対応できるモデルは一部に限られます。段差3cm以上や傾斜5%以上の現場では、四輪駆動タイプやサスペンション機構を持つ機種を検討してください。
- SLAM方式と磁気誘導方式はどちらが良いですか?
可変レイアウトや狭小スペースでの運用ならSLAM方式が有利です。固定レイアウトかつコストを抑えたいなら磁気誘導方式が適しています。
- 電池はどのくらい持ちますか?充電は面倒ではありませんか?
一般的に1回の充電で4〜8時間稼働します。最近のモデルは自動充電ドックを備えており、運用中のバッテリー切れの心配もありません。
- 搬送重量が30kg以下でもAGV導入の意味はありますか?
はい。軽量でも繰り返し回数が多い搬送業務は、人件費・時間・疲労軽減の観点から高い効果があります。手押し台車の代替として有効です。
- クリーンルームや病院などでも使用できますか?
可能です。防塵・静音・無排気設計の小型AGVや、医療施設向けに開発された抗菌対応モデルも存在します。
- 一度に複数台を連携させて運用できますか?
はい。フリート管理ソフトウェアを活用すれば、複数台の同時運用や経路最適化も可能です。複雑な運搬フローにも対応できます。
- レンタルやリースは可能ですか?
可能です。メーカーや代理店によっては、月額数万円からのリースプランやPoC(試験導入)サービスを提供しているケースもあります。
- 設置には工事が必要ですか?
SLAM方式やAMRであれば工事は不要です。磁気誘導型やQRマーカー型の場合、床面施工(マーカー設置)が必要になる場合があります。
- どのメーカーを選べば失敗しませんか?
製品選定は「使用環境」と「搬送条件」のマッチングが最優先です。特定メーカーにこだわらず、複数社の製品比較と試験導入を推奨します。
まとめ|小型AGV選びの最終チェックポイント
小型・超小型AGVは、限られたスペースでの搬送課題を解決するだけでなく、業務の自動化、標準化、省人化を実現する強力な選択肢です。特に「人が通れる幅さえあれば運用可能」という超小型モデルの進化により、これまで自動化が困難とされていた現場でも、導入可能性が飛躍的に高まりました。
AGVの導入に失敗しないために重要なのは、「サイズ」「機能」「搬送能力」「対応通路幅」などのスペックだけでなく、「自社現場の制約条件を的確に把握した上での選定判断」です。
以下の図解は、機種選定におけるポイントと導入フローを簡潔にまとめたものです。
AGV導入前チェックリスト
導入に際しての確認事項を漏れなく把握することで、失敗のない選定・導入が実現できます。
| チェック項目 | 確認すべき内容例 |
|---|---|
| 通路幅・旋回スペースの測定 | 最狭部の実寸確認(例:600mm以下) |
| 搬送物の重量・形状 | AGVの最大積載重量との適合性 |
| 搬送回数・頻度の把握 | ROIシミュレーションのための実績値 |
| 段差・傾斜・床材などの障害要因 | 走行方式(SLAM/磁気)との相性 |
| 自動充電・通信環境などのインフラ有無 | 自動充電ドック設置スペースや無線LAN環境など |
AGV選定において最も避けたいのは、「設置したが通路幅が足りなかった」「センサーが障害物を誤検知した」といった“現場とのミスマッチ”です。上記チェック項目を導入前に押さえることで、精度の高い選定と、運用トラブルの最小化が可能になります。
「うちは狭いから自動化は無理だろう」という思い込みを打破するのが、小型・超小型AGVの真の価値です。
そして、導入によって得られるのは、単なる「無人搬送」ではなく、作業の安定性・業務の継続性・現場の未来像の再設計という本質的な変化です。
現場で「あと数十センチの余白があれば」と諦めていた方こそ、最新の小型AGVに目を向けてみてください。
思った以上に、多くの現場が、自動化の“対象”になります
最適なAGVを導入するには、現場環境や運用目的に応じた選定がカギとなります。
比較のポイントを整理したチェックリストを含む資料を作成しました。
選定ミスを防ぐためにも、事前の情報収集にぜひお役立てください。
→ 選定チェックリスト付き資料を無料ダウンロード