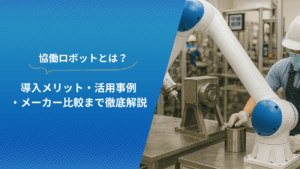「協働ロボットを導入しよう」と考えたとき、多くの現場担当者がまず手に取るのは“メーカー比較表”ではないでしょうか。
ですが──その「比較表」だけを頼りに選ぶことが、後々のコスト増・稼働トラブル・社内定着の失敗につながっていることをご存じでしょうか?
実際、多くの企業が価格やスペックだけで判断し、導入後に「想定通り動かない」「現場に馴染まない」と悩みを抱えているのが現実です。協働ロボットは、人と同じ空間で動き、現場業務と密接に関わる“戦略設備”。選び方を間違えれば、生産効率どころか現場の混乱すら招きかねません。
本記事では、導入目的・業務特性・将来拡張性・安全規格・教育体制など、見落とされがちな本質的な視点から「自社に本当に合った協働ロボットメーカー」の選び方を徹底解説します。
さらに、世界・国内・中国の市場動向や注目メーカーの比較、安全性評価のポイント、実際の成功・失敗事例まで網羅。
読み終える頃には、比較表の“その先”にある選定眼を手に入れ、「これならうちの現場に導入できる」と確信を持って判断できるようになります。
今この記事を読まないまま選定を進めるのは、未来の損失リスクを背負うことと同じです。
だからこそ、この記事で“最も合理的で失敗しない選定の答え”をつかんでください。
協働ロボット市場の現状とニーズ|世界・国内・中国の動向を解説
協働ロボットとは?産業用ロボットとの違いと主な用途
協働ロボット(コボット)は、人と同じ作業空間で安全に連携しながら働くことを目的としたロボットを指します。従来の産業用ロボットが主に柵や隔離された環境下で使われるのに対し、協働ロボットはセンサーや制御技術で安全性が確保されており、直接人間と接しながら作業が可能です。
主な用途は以下のとおりです。
- 製造業における組み立て、検査、材料供給などの自動化
- 非製造業分野でのサービス業、自動調理、医療現場での補助作業
- 中小企業の生産ラインでの多品種少量生産対応
産業用ロボットに比べ、小型・軽量でプログラムも直感的にできるため、導入や運用のハードルが低いことが協働ロボットの特徴です。
なお、協働ロボットの定義や活用事例について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
世界市場・国内市場・中国市場の成長動向と推進要因
世界の協働ロボット市場は急速に成長しており、2024年の出荷台数は約9万2,500台で前年比約48%増と大幅な伸びを示しています。2033年には7.4倍の約68万台に達するという予測もあります。市場規模は2025年時点で約116億米ドルに拡大し、2033年には約652億米ドルに達する見込みです。
特に中国市場は政府の支援策や製造業の自動化ニーズの高まりを背景に、2024年に前年比177%の驚異的な成長を遂げており、世界最大の需要国となっています。自動車およびエレクトロニクス業界において、自動化が遅れていた中小企業を中心に導入が加速。さらに、カフェのバリスタ用、飲食店の調理用、医療、農業など非製造業分野での活用も顕著です。

Factory DX
運営事務局
国内市場でも人手不足の深刻化、少子高齢化に伴う生産性向上の必要性から需要が拡大しています。
AI技術の進展により、非専門家でも使いやすい設定・プログラミングが可能になることで導入負担が軽減され、さらに市場拡大を後押ししています。
市場規模・出荷台数・導入事例から見る最新トレンド
2024年の世界の協働ロボット出荷台数は約9.2万台ですが、2033年までに7倍以上に拡大し、68万台規模に達すると予想されています。市場規模も身近になりつつあり、サービス型のロボット利用やモジュラーアームの多様化で、ユーザーの多様なニーズに柔軟に対応できるようになっています。
導入事例では、以下2点が特に注目されています。
これらの成功事例から、協働ロボットは従来の産業ロボットが苦手としていた多品種少量生産や人材不足補完に威力を発揮していることが読み取れます。
そのほかの業界における協働ロボットの導入成功・失敗事例については、こちらの記事もご覧ください。
協働ロボットの市場成長を支える主な要因
- 人手不足と少子高齢化: 生産現場での労働力不足に対する切実な対応策として導入が急増。
- AI・プログラミング技術の進歩: 操作の簡易化で専門知識不要に。
- 多様な使用用途: 製造以外のサービス業や医療・農業分野でも拡大。
- 政府支援と投資促進: 特に中国で顕著な支援策が市場成長を牽引。
協働ロボット市場の成長予測と主要推進要因
以下の表では、2024年時点の出荷台数と2033年までの予測を「世界・中国・日本」の3つの市場別にまとめ、成長を牽引する要因を整理しました。導入を検討している企業にとって、自社の判断が「業界全体の流れに合っているか」を確認する視点としてご活用ください。
| 市場 | 2024年出荷台数(台) | 2033年予測(台) | 主な推進要因 |
|---|---|---|---|
| 世界 | 約92,500 | 約680,000 | 人手不足、AI進展、多用途展開、投資活発化 |
| 中国 | 急増中(前年比177%) | 増加予測 | 政府支援、中小企業の自動化推進、非製造業領域拡大 |
| 日本(国内) | 増加中 | 増加予測 | 少子高齢化の生産性向上ニーズ、AI活用、製造現場改善 |
この表は、グローバル市場と各国別に協働ロボットの出荷台数と成長要因を一覧化したものです。特に中国では前年比177%の急成長が続き、政府支援と非製造業領域への拡張が大きな要因となっています。
一方、日本市場では少子高齢化に伴う人材不足を背景とした生産性改善ニーズが今後の導入を後押ししています。導入タイミングや競争優位性の確保に向けて、各国の成長スピードと背景を把握することは重要です。
協働ロボットメーカーの世界シェア・ランキングと特徴比較
2025年最新版|世界シェアランキングと台数・種類の傾向
2025年の協働ロボット市場は引き続き急拡大しています。市場シェア上位は、日本、中国、欧米の主要ロボットメーカーが競い合っており、各社は技術革新と多様な用途対応を武器に競争を繰り広げています。
世界の協働ロボットメーカーのシェア上位トップ10(2025年3月時点、複数情報源の統合データ)には以下のような企業が名を連ねています。
| 順位 | 企業名(英語) | 主な特徴 | 国・地域 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Universal Robots (UR) | 協働ロボットの草分け的存在。簡単な操作性と高い柔軟性。 | デンマーク |
| 2位 | FANUC | 大手産業ロボットメーカーが協働ロボット市場でも存在感。 | 日本 |
| 3位 | Yaskawa (安川電機) | 産業機械向けロボットで高い技術力を持つ。安全性に定評。 | 日本 |
| 4位 | KUKA | ドイツのグローバルロボット企業。自動車業界を中心に強み。 | ドイツ |
| 5位 | Techman Robot (TM) | AI搭載の協働ロボットで知られ、直感的なプログラミング。 | 台湾 |
| 6位 | AUBO Robotics | 中国発、技術力とコストパフォーマンスの高さが注目。 | 中国 |
| 7位 | Doosan Robotics | 韓国の新興勢力。産業用・サービス用双方への展開強化中。 | 韓国 |
| 8位 | DOBOT | 教育から産業まで幅広い用途。中国シェア急伸中。 | 中国 |
| 9位 | ABB | 技術革新と産業用ロボットに強く、協働ロボットも拡大中。 | スイス |
| 10位 | Han’s Robot | 中国大手。多品種少量生産への対応強化が特徴。 | 中国 |
このランキングは市場の成長の速さを反映し、特に中国勢の成長が著しいことが特徴です。中国メーカーはコスト競争力と政府支援を背景に世界市場へ積極的に進出しています。
協働ロボットの種類も多様化しており、5kg以下の小型機が最大シェアとなり、中堅の10kg以下、重荷重機も製造現場のニーズに応える製品開発が進行中です。AI搭載など先端技術を取り入れたモデルも増加し、操作の容易さや安全性の向上がユーザーの評価を高めています。
日本・中国・欧米の主要ロボットメーカーの実力と選定の勘所
協働ロボットの導入を検討する際、単に世界シェア上位のメーカーを並べて比較するだけでは不十分です。この記事では、日本・中国・欧米の代表的なメーカーについて、単なる製品特徴の羅列ではなく、導入現場での視点から「どのような企業にどのメーカーが向いているのか」までを掘り下げて解説します。
日本メーカー:高信頼性と現場適合性のバランス
FANUC(ファナック)
世界を代表するロボット企業であり、特に耐久性・安定性の面では群を抜きます。産業用ロボットでの実績が豊富で、大企業向けの大量生産現場に最適です。近年はAI・IoT連携機能も強化し、データ連携型のスマート工場構築に貢献しています。
安川電機(Yaskawa)
モーションコントロール技術の精度の高さは業界随一。サーボモータから協働ロボットまで一貫して高い制御性能を提供し、特に品質管理が厳しい現場や中小規模の自動化で強みを発揮します。導入・操作性のバランスも良く、教育体制も整っており初導入企業に向いています。
川崎重工
物流・搬送用途に特化したラインナップで知られます。大型機種や特殊用途に対応できる柔軟性があり、ライン間の搬送や仕分けなど工程の“つなぎ”を担うロボット導入に向いています。
中国メーカー:低コスト・高拡張性と急成長の勢い
AUBO Robotics
高い技術力と優れたコストパフォーマンスで注目される企業。多関節のスムーズな動作や、狭所作業への対応など小型機に強みがあります。製造ラインの一部自動化を進めたい中小企業におすすめです。
DOBOT
教育分野での導入実績も豊富で、直感的なプログラミングが可能。産業用としても汎用性が高く、安全設計が徹底されています。多品種少量の対応や複数拠点での展開を検討している企業に適しています。
Han’s Robot
多品種少量生産や柔軟な工程変更が求められる業種に対応できる設計思想を持ち、エレクトロニクスや精密加工分野での導入が増加中です。ロボットそのものだけでなく、周辺システムも一体提供する点が魅力です。
欧米メーカー:操作性と国際的サポートが強み
Universal Robots(デンマーク)
協働ロボット市場のパイオニアとして世界的な評価を確立。直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性が高く、中小企業や非製造業での導入事例も豊富です。日本国内にもサポート拠点を展開し、導入後の安心感も大きいです。
KUKA(ドイツ)
主に自動車業界での重作業・高精度作業に強みを持つメーカーで、モジュール化対応の製品が多い点も特徴です。ロボットアーム単体というよりは、ライン設計を含めた包括提案を得意とします。
ABB(スイス)
産業用ロボットの老舗企業として、特にグローバル企業の統合的な自動化ニーズに応える製品ラインを持ちます。AIやエッジコンピューティングとの連携も進み、スマートファクトリーの中核としての導入が進んでいます。
以下は、導入対象ごとのメーカー選定視点を整理した比較表です。
| 導入対象 | 推奨メーカー | 理由・特性 |
|---|---|---|
| 中小企業の自動化初導入 | UR、DOBOT、安川電機 | 操作性・価格・サポート体制が良好 |
| 大企業の多工程・大量生産 | FANUC、KUKA、ABB | 高耐久性とシステム提案力が強み |
| 柔軟な現場対応・工程変化 | Han’s Robot、TM Robot | モジュール設計・カメラ内蔵等に強み |
この表により、自社に最適なロボットメーカーの方向性が視覚的に把握しやすくなります。
補足:このように各メーカーは単なる「価格」や「スペック」では測れない、設計思想・技術強度・サポート体制といった“導入現場との相性”が存在します。協働ロボットは単なる設備ではなく、“運用までを含めた戦略資産”として評価すべきなのです。
中国メーカーの急成長と世界市場への進出状況
「価格だけで中国製を選んでいいのだろうか?」
そんな疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。実は今、協働ロボットの分野で中国メーカーが“低価格だから選ばれる”という従来の評価軸を超え、技術革新とグローバル戦略で世界市場を席巻しつつあります。
たとえば、AUBO RoboticsやDOBOT、Han’s Robotといった企業は、単に製品価格が安いだけでなく、「誰でも扱える操作性」「教育用途にも展開できる応用性」「小ロット・多品種の対応力」などで現場からの信頼を獲得しています。

Factory DX
運営事務局
これは中国政府の戦略的な支援だけでなく、「あえて日本や欧米が手薄だった領域」を徹底的に攻めたことも要因です。
とくに注目すべきは以下の2点です。
- 非製造業(教育・医療・飲食など)への適応を見越した製品設計
- デフォルトでAI・視覚認識を搭載し、現場の判断工数を削減
こうした“実務ニーズに即した革新”が、今の中国勢の強みとなっています。
中国協働ロボットメーカーの特徴と戦略比較
以下の表は、代表的な中国メーカー3社の特徴と市場戦略を比較したものです。
| メーカー名 | 技術的特徴 | 対応業種 | 海外展開の重点エリア | 注目の競争力 |
|---|---|---|---|---|
| AUBO Robotics | 拡張性・安全性重視、軽量設計 | 製造業・研究開発 | 欧州・アジア圏 | ISO規格対応、OEM多数 |
| DOBOT | 教育〜産業一貫対応、操作性に強み | 教育・製造・小売 | 東南アジア・北米 | 導入支援ツールが豊富 |
| Han’s Robot | 多品種生産向け、視覚認識に注力 | 製造業・医療・物流 | 欧州・中東 | システム統合の柔軟性 |
表内の情報は、各社の製品カタログおよび公式発表に基づいて整理したものであり、日本国内でも実際に導入が進んでいる事例があります。
このように、中国メーカーは“価格×技術”の両軸で差別化を図っており、単なる「低コスト」だけではない本質的な競争力を備えています。
たとえば、AUBO Roboticsでは日本国内の中堅製造業者が設備入れ替え時に採用し、導入後すぐに現場で定着したケースも確認されています。
結果として、次のような導入メリットを実現できた事例もあります。
- 稼働初日から従業員による再設定が可能なレベルの操作性
- センサ類や安全機構を現場仕様に柔軟に変更できる汎用性
導入に迷った際、「中国製=安かろう悪かろう」ではなく、「中国製=現場で即戦力になる存在」として再評価する視点を持つことが、結果的に最も合理的な選定につながる可能性があります。
中国協働ロボットメーカーの強みと背景|ランキングから見る競争力
中国協働ロボットメーカーの国内・世界シェア動向
中国協働ロボットメーカーは国内市場で急速にシェアを拡大しており、世界市場においても存在感を高めています。特にAUBO Roboticsは、中国国内の協働ロボット出荷台数で5年連続トップシェアを獲得し、世界市場でも上位に位置付けられています。価格競争力と技術力の両立が強みであり、中国メーカーは市場をほぼ独占している状況です。
主要中国ロボットメーカー一覧(例:エスタン、エファイ、AUBO等)
近年、急速に台頭している中国協働ロボットメーカーの中でも、特に注目される企業をピックアップしました。各社の強みや技術的な特徴を整理することで、メーカーごとの違いや選定時の比較ポイントがより明確になります。
| メーカー名 | 主な特徴 |
|---|---|
| AUBO Robotics | 競争力のある価格、幅広い負荷対応製品、高い技術力 |
| DOBOT | 教育・産業向けロボットの多様なラインアップ、安全性と直感的操作が強み |
| Estun (エスタン) | 制御システムとサーボ技術に強み。産業向け高性能ロボットを提供 |
| Efort (エファイ) | 高精度な産業用ロボットを展開。欧州企業買収による技術連携が注目 |
| JAKA Robotics | AI・スマート機能搭載の協働ロボットで市場リーダーの一角 |
| Han’s Robot | 多品種少量生産向けに対応。大手中国企業として世界展開も進めている |
この表は、中国の主要な協働ロボットメーカー6社について、製品特性や競争力の焦点を簡潔にまとめたものです。特に、技術力と価格面でのバランス、国際展開力、用途の多様性において強みを持つ企業が選定されています。自社に合ったパートナー選びの際の参考情報として活用してください。
この一冊が、導入後の後悔をゼロにします
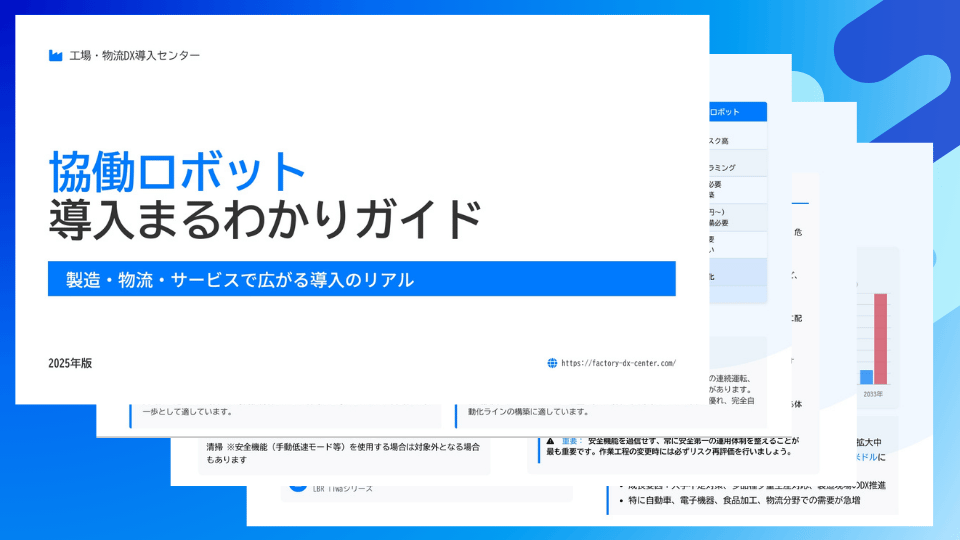
導入後に気づいても遅い——。
協働ロボットで失敗する企業が必ず見落とした「安全設計と工程設計の盲点」を一冊に凝縮しました。
確認するだけで、余計なコストや手戻りを大幅に削減できます。
中国メーカーの技術力・価格・拡大戦略のポイント
- 技術力
多くの中国企業はAIや画像認識を組み込んだスマート協働ロボットを開発。国内独自の技術開発だけでなく、海外企業の技術買収や提携によりイノベーションを加速しています。 - 価格競争力
中国国内の企業環境を背景に、コストパフォーマンスに優れた製品を投入。中小企業や新興企業にとって導入しやすく、市場規模拡大を支えています。 - 拡大戦略
国内政府の強力な支援策を活用し、積極的に海外市場にも進出。東南アジアや欧州を中心に販売網を広げ、グローバルシェア拡大を狙います。
中国政府の産業推進政策とAI・自動化需要の影響
中国政府は「中国製造2025」政策でロボット産業の自立を強力に推進しており、国産ロボットメーカーの競争力強化に資金援助や制度面のバックアップを提供しています。これにより、国内市場は旺盛な自動化需要を背景に急速に拡大。
また、AI技術の統合により協働ロボットの安全性と操作性が向上し、人手不足や製造現場の多様なニーズに応える形で需要が増加しています。政府支援を受ける企業は研究開発投資を増やし、技術革新を牽引しています。
中国協働ロボットメーカーの強みと競争力概要
以下の表は、中国主要協働ロボットメーカーの強みとその背景を簡潔にまとめたものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 技術力 | AI・スマート機能搭載、高精度制御、国産技術+海外提携 |
| 価格競争力 | 高いコストパフォーマンス、中小企業に導入しやすい設計 |
| 市場シェア | 国内出荷数トップクラス、世界シェア拡大中 |
| 政府支援 | 「中国製造2025」政策による投資・助成、産業振興策が強力 |
| 拡大戦略 | 東南アジア、欧州市場進出加速、グローバル拡大を狙う |
この表は、読者が中国メーカーの競争力の全体像を俯瞰しやすいようにまとめたものです。特に技術力と政府支援の相乗効果が市場拡大の最大要因として注目されます。
協働ロボットメーカー比較だけでは失敗? 導入前に押さえるべきポイント
価格やスペックだけで比較するリスクと注意点
協働ロボットの導入検討時に、価格や基本スペックの比較だけで決定すると、後々のトラブルや期待違いのリスクが高まります。なぜなら、協働ロボットは単なる製品の性能だけでなく、導入環境や業務内容に密接に関わるため、以下のような注意点があるからです。
- 安全性の確保は製品スペックだけでは不十分
協働ロボットは人と同じ空間で動作するため、ISOやIEC規格に合致する安全機能が必須ですが、安全対策は製造現場の環境・人の動きに合わせて適切に設計・評価されなければなりません。単純にスペックが高いだけなら安心というわけではなく、リスクアセスメントが不可欠です。 - サポート体制の違いによる運用トラブルリスク
ローカルでの技術サポートやメンテナンス体制の充実度が低いと、トラブル発生時に迅速な復旧が困難になります。特に中小企業ではリソースが限られるため、手厚いサポートがあるメーカーかどうかは重要です。 - 適合性の見落としによる導入失敗
業務内容や作業環境に合わせたモデル選定やカスタマイズを怠り、汎用モデルのみで導入すると、結果的に業務効率向上が見込めなかったり、現場の使い勝手が悪くなったりします。
協働ロボットの導入は、「製品スペックの比較」や「価格の検討」だけでは不十分です。実際に現場で“動く”ためには、安全性・サポート体制・業務適合性といった見えにくい要素が導入成否を大きく左右します。
特に、中小企業や初導入の企業ほど、「使える」ではなく「使いこなせる」ことが重要であり、そのためには設置前のリスク評価、導入後の支援体制、現場環境との相性といった視点を欠かさずに押さえる必要があります。

Factory DX
運営事務局
選定時は、カタログに現れない“運用視点”でのチェックが極めて重要です。
目に見える機能だけでなく、運用後の安定性と成果まで見越した判断こそが、協働ロボットを本当の意味で現場の戦力にするための分岐点となります。
現場導入で重視すべき安全性・ローカルサポート・導入実績
協働ロボット導入時にまず重点的に押さえるべきポイントとして、以下が挙げられます。
- 安全性の具体的な評価と機能
協働ロボットの安全性は、単に「人が当たっても怪我をしない」だけでなく、レーザースキャナー、ライトカーテン、衝突検知といった多層的な安全機構が組み込まれているかが大切です。例えば実際の導入では、リスクアセスメント後に安全柵なしでの運用を可能にするため、複数の安全装置配置と機械の動作停止の仕組みが必須となります。 - ローカルサポートとメンテナンス対応
メーカーや販売代理店が現地で技術支援を提供できる体制かどうかは、システム故障時のダウンタイム短縮に直結します。導入後のトレーニング、トラブルシューティング、アップデート対応まで一貫したサポートがあることが望ましいです。 - 導入実績の確認
業種や似た用途での成功事例が豊富にあるか確認することも重要。実績があると、運用ノウハウや問題解決策が蓄積されているため、安心感が高まります。
用途・業務に最適な種類・シリーズ選定の方法
用途に応じたロボットの種類やシリーズ選択は導入効果の大きな鍵です。スペック上の数値だけでなく、以下を検討しましょう。
- 作業負荷(扱う物の重量や高さなど)に合ったペイロードの選定
- 動作範囲や設置スペースの制約への適合性
- 拡張機能の有無(グリッパーやセンサーの互換性など)
- プログラミングの容易さや既存設備との連携性
適切な選定は後の運用コスト低減と現場の使いやすさ向上につながります。
ティーチングや拡張性、AI活用等の新技術への対応
急速に進化する協働ロボット技術ではティーチング(動作教示)が簡易かつ直感的であることも重要です。これが現場スタッフの導入と習熟にかかる負担を大きく軽減します。
また、以下の新技術対応も導入判断の重要ポイントです。
導入前に押さえるべき協働ロボット選定の主要項目
下記の表では、現場で本当に重視すべき比較項目を、目的別に整理しています。導入後の運用トラブルや失敗リスクを回避するためにも、事前にこれらのポイントを一つずつ丁寧にチェックしておくことが重要です。
| 項目 | 内容概要 |
|---|---|
| 安全性機能 | 衝突検知、速度監視、エリアセンサ(レーザースキャナー等)搭載状況。ISO/IEC規格適合の有無も確認。 |
| ローカルサポート | 地域での技術支援、メンテナンス対応の充実度。トラブル時対応スピード。 |
| 導入実績 | 同業種・同規模の事例数。成功事例の有無が信頼性の指標となる。 |
| 用途適合性 | 作業内容、環境に適したペイロードや動作領域の判断。 |
| 操作性・拡張性 | ティーチングの簡易性、AI搭載の有無、外部機器連携のしやすさ。 |
この表は、導入時に見落とされがちな「実務目線での確認項目」をまとめたものです。とくに安全性やローカルサポートの充実度は、設備の稼働率やトラブル時の損失に直結します。
また、用途や操作性の適合性は、導入後の“使われ続けるロボット”となるかどうかを左右する決定的な要因です。導入判断の際には、単に製品仕様を比較するのではなく、このような実務軸での評価を加えることで、失敗リスクを大幅に軽減できます。
導入成功のための協働ロボットメーカー選定ステップ
協働ロボットの導入で最も大きな落とし穴は、「メーカー選定=カタログ比較」で完結してしまうことです。
製品ごとの性能差よりも、導入目的の明確化、業務との適合性、現場に根付くサポート体制といった“選定プロセス”の質が、導入成果を大きく左右します。
ここでは、導入を成功させるために最低限押さえておきたい4つのステップを、現場実務の視点で解説します。
導入目的と自社業務・現場ニーズの明確化
まず前提として、なぜ協働ロボットを導入するのか、導入によってどの業務を改善したいのかを言語化することが最優先です。目的が曖昧なままでは、メーカー選びも導入設計もすべてがズレてしまいます。
例えば「人手不足の補填」「作業品質の安定化」「属人化の解消」といった目的はよくありますが、それに応じて必要な機能や適した製品タイプが全く異なります。
また、「どの作業工程に適用するか」「作業員のスキルレベル」「作業サイクル」「工数と設置スペースの制約」など、現場の制約条件も同時に明確化することが必要です。
機種・シリーズ選びのチェックポイント
導入目的と現場条件が整理できたら、次にロボットの選定に入ります。ここで重要なのは、単に「一番多機能な機種を選ぶ」のではなく、「目的と制約に最も合ったものを選ぶ」ことです。
以下の観点で選定することが失敗回避のカギとなります。
- 作業内容に対して適切なペイロード・可動範囲か
- 設置スペースに合うサイズ・動作軌道か
- カスタム機器との連携可否(グリッパー、カメラなど)
- ティーチングやソフトの操作性は現場で対応可能か
- 他工程との自動連携(コンベア制御、センサ信号など)が構築しやすいか
特に“設置後に作業に合わなかった”という失敗は、導入前の動作シミュレーションやデモ検証で防げます。
メーカー・代理店のサポート体制と国内外の違い
メーカー比較で見落とされがちなのが、サポート体制の質と地域対応力です。特に協働ロボットのような“現場で止まっては困る設備”では、トラブル発生時にどれだけ早く対応できるかが決定的な要素になります。
チェックすべきポイントとしては以下の通りです。

Factory DX
運営事務局
日本企業の多くは、言語や時差によるサポート遅延に対して不安を抱えています。その点も含め、国内サポート体制の実績があるメーカーは安定運用の観点で有利です。
比較表・選定フローで分かる失敗しない導入方法
協働ロボットのメーカー・機種選定には、主観だけでなく客観的なチェックリストが不可欠です。以下の表では、失敗を避けるために必要な視点をフロー形式で整理しています。
| 選定ステップ | チェックポイント例 |
|---|---|
| 導入目的の明確化 | なぜ導入するか?どの業務を改善するか?改善指標(KPI)は? |
| 現場条件の整理 | 作業スペース、安全性、搬送物、工程内の位置関係など |
| 機種選定 | ペイロード、軌道、操作性、拡張性、制御ソフトとの互換性 |
| メーカー・代理店評価 | サポート体制、技術対応の質、保守契約、納期、国内代理店の対応力 |
| 実機デモ・導入検証 | シミュレーション実施、現場でのトライ導入、ティーチング研修実施など |
この選定フロー表は、協働ロボットの導入前に企業側で把握・確認しておくべき実務項目を体系的に整理したものです。カタログスペックや価格表だけでは見えてこない「使える・続けられる・止まらない」ための選定基準が詰まっています。
特に初導入や自社内でエンジニアを常駐できない企業にとっては、この流れに沿った選定こそが導入後の失敗を防ぐ唯一の手段となります。
協働ロボットメーカーに関するよくある質問と回答集
- 協働ロボットメーカーを選ぶ際に最も重要視すべきポイントは何ですか?
基本性能(可搬重量、リーチ)を自社作業に合致させることに加え、安全性の充実、操作のしやすさ、サポート体制の手厚さ、拡張性の有無が重要です。これらを総合的に比較検討してください。
- 国内メーカーと海外メーカー、どちらを選ぶべきでしょうか?
国内メーカーは日本市場に適したサポートや法規対応が充実し、海外メーカーは最新技術や幅広い製品ラインナップを強みとしています。現地サポートや導入実績、メンテナンス体制を含めトータルで判断しましょう。
- メーカーごとの導入コストやランニングコストの違いはどの程度ありますか?
本体価格だけでなく、メンテナンス費用、部品交換、ソフトウェア更新、トレーニング費用も総合的に評価する必要があります。メーカーによって保守契約の内容や費用体系が異なるため、比較の際は詳細確認が欠かせません。
- 導入後のトラブル時、メーカーのサポート体制はどのように確認すれば良いですか?
国内にサービス拠点を持っているか、対応時間、代替機貸与、現地技術者の派遣可能か、問い合わせ対応スピードなどを事前に問い合わせて確認してください。充実したサポートが稼働率維持に直結します。
- 協働ロボットメーカーは製品以外にどんな付加価値を提供していますか?
トレーニングプログラムや、使いやすさ向上のためのソフトウェアアップデート、豊富な周辺機器・アクセサリーのエコシステム提供、コンサルティングサービスや導入支援など多様な付加価値があります。
- 協働ロボットメーカー間でのAI活用技術の違いは具体的にどこにありますか?
メーカーによって、AIの適用範囲が異なります。画像認識の精度、異常検知機能の高度さ、自律動作の判断アルゴリズム、さらにクラウド連携や機械学習による性能向上の仕組みまで多彩です。これらは製品の操作性や生産性に直結します。
- 協働ロボットメーカーの安全機能基準でISO/TS 15066への準拠状況はどのように確認すべきですか?
メーカーの技術資料や認証書類で準拠状況を確認し、導入環境に合わせたリスクアセスメント支援の有無も確認することが大切です。対応レベルによって、安全柵不要での運用が可能かどうかも変わります。
- メーカーごとに異なるティーチング方式やプログラミング環境の違いは導入後にどんな影響を与えますか?
ティーチング操作の難易度や柔軟性は、導入後の生産変更やライン改装時の対応コストに影響します。ドラッグ&ドロップ式やAI支援型は教育負担を減らし、現場のスムーズな運用に寄与します。
- 協働ロボットメーカーの製品でモジュール化やアップグレード可能な設計の普及状況は?
多くの先進メーカーがエンドエフェクタやセンサーの交換可能なモジュラー設計を採用し、IoT連携機能を追加できる製品を投入しています。これにより現場の変化に応じて機能追加が容易になり、長期的な投資効率が向上します。
- 中国メーカーの急成長が協働ロボット市場に与える影響と、日本・欧米メーカーとの技術戦略の違いは?
中国メーカーはコスト競争力とスピード感を武器に急速にシェアを拡大。AI搭載モデルの技術革新や政府支援政策が後押ししています。一方で日本・欧米は高信頼性・高耐久性と専門的用途対応を強化し、差別化戦略をとっています。
後悔しない協働ロボット選び|「現場で本当に使える」メーカーを見極める
協働ロボットの導入において「メーカーを比較して選ぶ」という行為は、決して間違いではありません。しかし、“比較の視点”を間違えると、導入後の運用段階で多くの企業が「思ったほど成果が出ない」「トラブルが頻発する」といった壁に直面します。
このような事態を避けるためには、以下の2点を忘れてはいけません。
また、初期費用や性能の良し悪しよりも、「導入してから半年後、1年後に現場でどれだけ効果を発揮しているか」という視点でメーカーや機種を選ぶことが、結果的に最も大きなコストパフォーマンスを生むポイントです。
導入判断を間違えないための視点整理
導入時に見落としやすいポイントを下記に図解として整理しました。メーカー選びの軸を最終確認する際のチェックにご活用ください。
| ステップ | 内容の要点 |
|---|---|
| 目的の明確化 | なぜ導入するか?どの業務をどう改善したいか |
| 現場ニーズの整理 | 作業内容・人員配置・既存設備との兼ね合いなど |
| 導入制約の確認 | 設置スペース、初期コスト、工数・時間的余裕など |
| ロボット選定 | ペイロード、拡張性、操作性、シリーズの適合性など |
| サポート・実績・リスク評価 | サポート拠点の有無、実績、保守対応・緊急対応体制 |
| 最終確認:現場での定着と成果実現 | 導入後に「現場で使われるか」「成果が出るか」 |
この表は、単に製品を導入するだけでなく「現場で成果を出すまで」のプロセスを可視化したものです。とくに導入前の時点で、「定着」と「成果」を見越した逆算型の判断ができるかどうかが、協働ロボット投資の成否を分けます。
カタログや価格比較だけではたどり着けない“現場視点での納得感”が、最終的に後悔しない選定を実現します。