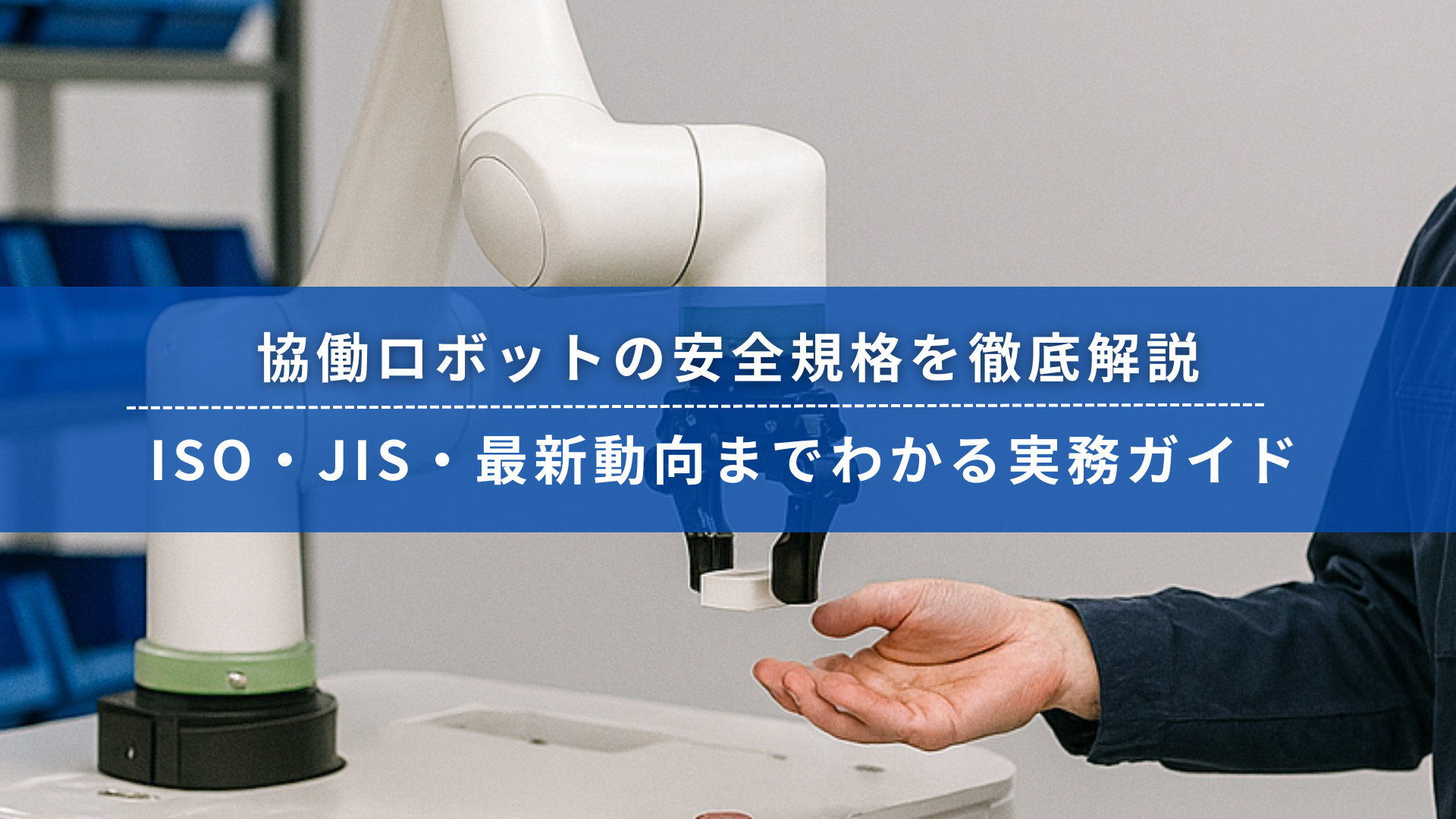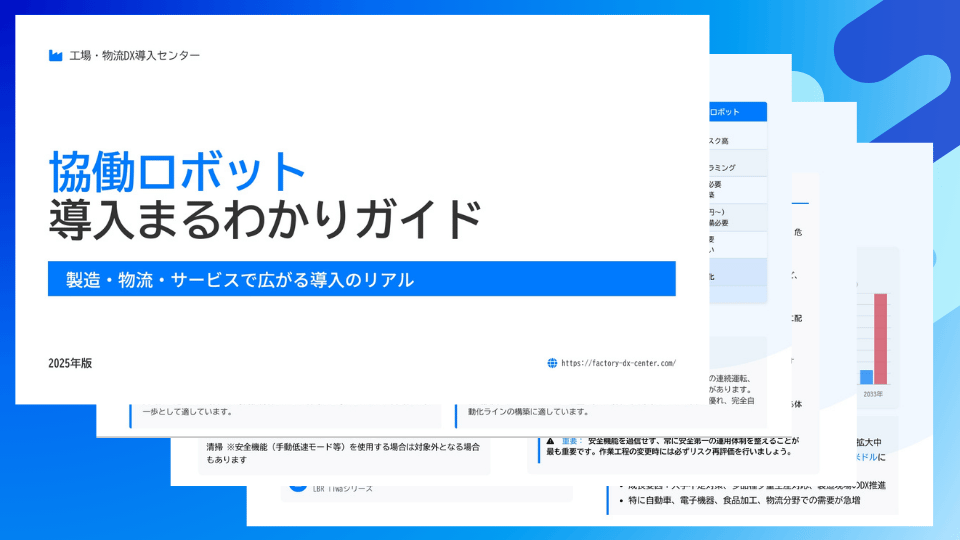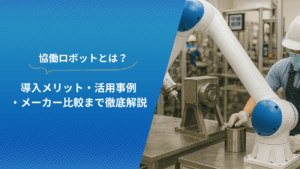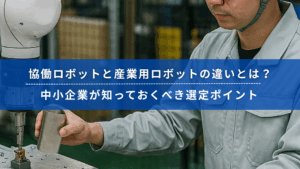「協働ロボットを導入したいが、安全規格への対応がよく分からない」
「そもそも、ISOやJISって現場にどこまで関係するの?」
こうした声は、製造現場の責任者や導入プロジェクト担当者から日常的に聞かれます。
実際、協働ロボットの導入は年々加速しており、技術的なハードルは以前よりも大きく下がっています。しかしその一方で、「安全規格への不十分な理解」が原因で、監査対応や事故リスク、保険料増など“見えないコスト”が後になってのしかかるケースが増えているのも事実です。
特に2025年のISO改訂をきっかけに、従来の「囲っていればOK」という安全設計の常識が通用しなくなりつつあります。もはや「安全規格の理解=設備投資の前提」であり、それを外すと設計段階から見直しになるリスクさえあります。
本記事では、協働ロボットに関わる安全規格を、ISO・JIS・最新の国際動向を交えて徹底的に解説します。
読んでいただくことで、安全設計の勘所と導入の優先順位がクリアになり、設計ミスや後戻りコストを防ぐ判断力が身につきます。
今この段階で、きちんと理解しておくことが、導入後の安心と信頼につながります。
そのための“実務ガイド”として、ぜひ最後までご活用ください。
協働ロボットと安全規格の関係性とは?
なぜ協働ロボットには特別な安全設計が必要なのか
協働ロボット(コボット)は、人と同じ作業空間で協力しながら作業することを前提に設計されたロボットです。これは、従来の産業用ロボットとは大きく異なります。従来ロボットは安全柵や囲いの中で人と物理的に分離されており、そもそも接触を前提としていませんでした。
しかし協働ロボットは、人との接触リスクが日常的に存在します。たとえば、作業員と並んでピッキング作業をしたり、部品の受け渡しをしたりと、身体が至近距離にある状態で動作します。こうした作業形態では、わずかな衝突や誤動作が重大な事故につながるリスクがあるため、明確な安全設計の基準が不可欠となります。
協働ロボットの基本的な特徴や導入メリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
また、協働ロボットの導入現場ではロボットに詳しくない中小企業や多品種少量生産ラインが多く、安全に関するノウハウや体制が十分でないケースも少なくありません。こうした状況下で安全規格が果たす役割は非常に大きく、設計者・導入担当者・保守管理者が共通の判断基準を持つための「共通言語」として機能します。
加えて、ISO規格のような国際基準は、機械メーカー・システムインテグレーター・エンドユーザーが安全を担保しながら協業する際の「契約上の参照文書」としても使われます。つまり、安全規格の存在がなければ、誰がどこまで安全に責任を持つのかが曖昧になり、結果として労働災害リスクの増大や導入トラブルを引き起こす恐れがあるのです。
安全規格が重要視される背景(導入加速・規制緩和など)
近年、少子高齢化による人手不足を背景に、製造業・物流業界を中心に協働ロボットの導入が急速に進んでいます。その一方で、「安全性への不安」を理由に導入を躊躇する企業も多いのが現実です。こうした現場の声を受け、国際的にも国内でも安全規格の整備が加速しました。
とくに大きな転換点となったのが、日本国内における労働安全衛生規則の一部緩和(80W規制の適用除外)です。この制度変更によって、条件を満たせば事前審査なしで協働ロボットの導入が可能になりました。これは、企業側の導入ハードルを大幅に下げる一方、導入者側の「自己責任によるリスク評価」が強く求められるようになったことを意味します。

Factory DX
運営事務局
つまり、安全規格は単なる「お役所仕事のルール」ではなく、導入企業が自ら現場を守るための盾であり、業務を継続的に回すための戦略的ツールとして活用されるべきものなのです。
協働ロボットを溶接工程に導入した場合のリスク評価や導入効果については、こちらの記事で具体的に紹介しています。
安全規格が果たす3つの役割
以下は、安全規格が現場において果たす役割をシンプルに整理した表です。
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| ① 安全性の担保 | 人と機械の接触リスクを最小限に抑える |
| ② 責任範囲の明確化 | 設計者・製造者・使用者の責任線引き |
| ③ グローバル対応・法令順守支援 | ISO/JIS基準で国際的信頼性を確保 |
このように、安全規格は単なる技術的なルールではなく、企業の「製品品質」「労働環境」「法的リスクマネジメント」すべてに関わる極めて実践的な基準です。
実際の導入現場では、安全性の検証だけでなく、外注管理や保険契約、現場教育など複数の業務でこの3つの視点が問われるため、経営的視点からの理解にもつながります。
代表的な協働ロボットの安全規格一覧 【ISO・JIS・国際基準】
協働ロボットを安全に運用するためには、各種の国際規格および国内規格の理解が欠かせません。これらの規格は設計・製造・運用・保守の各フェーズで「どこまで対策すれば安全といえるのか」を判断する指針となります。
ここでは、協働ロボットに関わる主要な安全規格を、実務者の目線でわかりやすく整理して紹介します。
ISO 10218-1/-2(ロボットとシステム設計の基本規格)
この規格は、産業用ロボットとそのシステム全体に求められる安全設計基準を定めた国際規格です。
ISO 10218-1はロボット本体、ISO 10218-2はロボットシステム全体(制御系・防護手段など)に関する要求事項を扱っています。
これらは、機械指令2006/42/ECにも適合する形で構成されており、ヨーロッパをはじめとする多くの国々で「製品安全証明の根拠」として使われています。
特に2025年の改訂では、協働ロボットに関する設計要件が大きく強化され、ISO/TS 15066の内容が統合されたことで、より実践的かつ具体的な安全基準に進化しています。
ISO/TS 15066(協働作業の力・速度制限などの追加仕様)
ISO 10218では網羅しきれなかった「人との物理的接触が前提となる作業形態」に特化して設けられたのがISO/TS 15066です。
この技術仕様では、協働ロボットが人と接触する際の力・圧力・速度などの安全許容値が詳細に数値化されています。これにより、実際のロボット導入時にどの程度の力でどの部位に接触すれば安全かを客観的に評価できます。
また、4つの協働作業モード(安全停止・手動ガイド・速度/間隔監視・力/圧力制限)ごとに必要な制御機能も明確に定義されています。

Factory DX
運営事務局
2025年の改訂により、このTS規格の主要内容はISO 10218に吸収されましたが、技術仕様としての位置づけが本編に統合されたことで、実運用への影響度は一層大きくなっています。
JIS B8433シリーズ(日本国内向け翻訳規格)
JIS B8433-1およびJIS B8433-2は、それぞれISO 10218-1/-2をベースにした日本国内向けのJIS規格です。
基本的にはISOと同等内容ですが、国内法令(労働安全衛生法、労働安全衛生規則など)との整合をとるための記述が補足されており、日本企業にとってより現場で活用しやすい内容になっています。
また、国内で「協働ロボットを法令に適合して導入するには何を満たせばいいのか?」という疑問に対して、JISの視点は実務上の明確な答えになります。
その他関連規格(ISO 12100、ISO 13849、IEC 61508など)
協働ロボットの安全を確保するうえで、単体の規格では対応しきれない設計要素も存在します。
以下のような関連規格も組み合わせて適用することで、総合的な安全性を実現できます。
各安全規格の位置づけと関係性
| 規格名 | 位置づけ | 主な内容・役割 |
|---|---|---|
| ISO 12100 | 安全設計の基本方針(最上位) | 機械安全の基本原則とリスクアセスメントの枠組み |
| ISO 10218-1/-2 | ロボット設計・システム設計の基準 | ロボット本体や導入環境における構造・制御・設置要件 |
| ISO/TS 15066 | 協働モードの補足仕様(ISO 10218に従属) | 人との接触に関する力・圧力の制限値、協働空間設計基準 |
| ISO 13849 | 制御系の信頼性評価(技術支援規格) | 非常停止や安全回路における性能レベル(PL)の評価基準 |
| IEC 61508 | 電気・電子・機能安全の評価(技術支援規格) | システム全体の機能安全を評価するためのSIL定義 |
この表では、ISO 12100をベースとした安全設計方針の上に、設計(ISO 10218)、運用(ISO/TS 15066)、制御(ISO 13849/IEC 61508)が重層的に積み上がっている構造を示しています。これは、どの段階でどの規格を参照すべきかを整理するうえで非常に実用的な観点です。
【最新情報】 2025年改訂でどう変わる?ISO 10218と15066統合のポイント
改訂の背景とスケジュール
ISO 10218シリーズは、産業用ロボットの設計者およびシステムインテグレーターに向けた安全基準として2011年に策定され、その後ISO/TS 15066が補完的に登場することで、協働作業における安全性がより現場に即したものとなりました。
しかし、TS 15066は技術仕様であり、強制力のある正式な規格とは位置づけが異なっていました。そのため、運用者や審査機関の間で「どこまで遵守すべきか?」の判断にばらつきが生じ、結果として現場での運用混乱や安全水準のばらつきが課題になっていたのです。
この背景を踏まえ、ISOは2025年に改訂を行い、ISO/TS 15066の内容を正式にISO 10218シリーズに統合。協働作業を正式に構造化された安全設計の一部として位置づけることになりました。
改訂スケジュールとしては、2025年2月に正式に発行されており、ISO/TS 15066の内容を統合した新たなISO 10218シリーズ(-1/-2)が公開済みです。これにより、従来のDIS(Draft International Standard)段階の内容は確定し、各国における規格対応や実務運用への移行が始まっています。
統合後の安全要件と新たな設計指針
2025年版ISO 10218では、以下の3つの観点から設計指針が強化されます。
特に注目すべきは、ISO 10218-1に「協働ロボット本体の設計上の安全条件」が追加され、従来はTS 15066で参照されていた接触圧・衝突速度・力制限値などの定量データが正式に規格本文内に組み込まれた点です。
規格設計の実務者目線で見る「統合の意味」
実際の設計現場では、「ロボットメーカーはISO 10218-1までを満たせばよい」とされ、TS 15066についてはユーザー責任とされることが多くありました。
しかし、統合後はロボットメーカーと使用者の双方に協働作業安全の設計責任が共通して課される構造となり、境界線が曖昧だった部分が契約上明確化されます。
この変更は、導入契約書や安全審査書類において、「協働運用におけるリスク評価と設計方針」が標準フォーマット化される動きを加速させることを意味します。
また、ISO 10218-2には、エンドエフェクタ(ツール)側の安全設計要件も新たに追記され、これまであいまいだった「ロボット+周辺機器を含めたシステムとしての安全性」が審査の対象となることが明確になります。
統合が変える3つの視点
以下に、ISO統合によって実務にどう影響するのかを整理した表を提示します。
| 区分 | 変更前:責任分離 | 変更後:共同責任+共通設計基準 |
|---|---|---|
| メーカー | ISO 10218 のみ遵守 | 使用者と共通の設計責任範囲をISO 10218:2025で明記 |
| 使用者 | ISO/TS 15066の判断・運用に委ねる | 協働仕様も含めて共通基準を遵守(TS15066の内容が統合) |
| 設計対象 | ロボット本体中心 | エンドエフェクタや周辺装置も含む設計基準が追加 |
この構造的な変化は、導入企業にとって「判断の自由度が減る」ことでもありますが、それは同時に安全品質が契約上の保証範囲として明文化され、訴訟リスクや事故発生時の責任論を曖昧にしないメリットでもあります。
導入企業に求められる対応の変化
2025年の規格統合により、導入企業が準備すべきは以下の通りです。
そもそも自社に適したロボットの種類を見極めるためには、協働型と産業用ロボットの特性を正しく理解することが重要です。詳しくはこちらをご覧ください。
特に、サイバーセキュリティ要件については「なにをもって安全とするか」が未整備な企業も多いため、ITセキュリティ部門との連携を早期に進めることが鍵となります。
今後、認証機関や保険会社もこの新規格をベースに安全基準の審査やリスク評価を行う可能性が高いため、現場レベルだけでなく経営層レベルでの理解・対応が求められます。
協働ロボットの安全規格に基づく「リスクアセスメント」実務ステップ
ISO 12100に基づくリスク評価の流れ
協働ロボットの安全設計において、最初にして最も重要なプロセスが「リスクアセスメント」です。ISO 12100はその基本規格であり、すべての機械安全の“共通言語”として世界中で用いられています。
この規格では、危険を見つけ、リスクを見積もり、評価し、対策を講じるという4ステップが定義されています。しかし、実際の現場では「どの粒度で評価すべきか」「安全対策は設計でどこまでやるべきか」が悩みのタネです。
ここで押さえるべきポイントは、形式的に全体を網羅するのではなく、接触する“作業者の行動パターン”に合わせて評価軸を絞るという設計思想です。つまり、協働ロボットでは「人の動き方と判断ミス」を含めたリスク設定こそが実務の要となります。
リスクアセスメントを“人の視点”で再構成する4ステップ
以下は、ISO 12100のプロセスを「人の動きと判断」に焦点を当てて実務ベースで再整理したものです。
| ステップ | 内容の要点 | 補足説明 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 危険を発見する前に「人の動き」を観察せよ | 作業姿勢、移動経路、注意の向きなどを丁寧に観察すること |
| ステップ2 | 発生確率ではなく「気づきの有無」でリスクを評価 | 気づけない危険=高リスクとみなし、優先的に対策する |
| ステップ3 | リスクを分類し「許容できる」かで線を引く | 判断基準は不可避性・頻度・致命度の3つの観点から |
| ステップ4 | リスク低減策は「動作制限 → センサ → 教育」の順で実施 | 対策の優先順位を明確にし、実効性のある措置を取る |
このように、ISO 12100の考え方を単なるマトリクス評価にとどめず、作業者の挙動分析と組み合わせて運用することで、「現場で再現できるアセスメント」へと変えることができます。
TS 15066での力・圧力の測定基準
ISO/TS 15066は、協働ロボットが人と接触することを前提とした唯一の数値規格です。ここで示される「接触許容値(力・圧力)」は、マネジメント層ではあまり注目されませんが、実は安全設計の“合否”を左右する最もシビアな基準です。
この規格では、人体を29部位に分け、それぞれに「痛みを伴わず損傷もない接触限界値」が明記されています。たとえば、上腕と指先では許容値に大きな差があります。にもかかわらず、多くの現場では「力制限=一律の出力設定」として処理してしまう例が後を絶ちません。

Factory DX
運営事務局
ここで提案したいのが、「作業内容と接触部位を紐づけてシナリオ別に評価する」方式です。
この方式では、たとえばピッキング、ねじ締め、部品供給といった作業ごとに、接触しうる部位をリストアップし、それぞれの許容値と照合する。このプロセスを通じて、汎用的な安全制御ではなく「作業に合った現場設計」が可能になります。
残留リスクと文書化の方法
どんなに対策を施しても、すべてのリスクをゼロにすることは不可能です。ここで必ず登場するのが「残留リスク」という概念です。
ISO 12100では、この残留リスクを明文化し、関係者間で共有すること自体が安全設計の一部であるとしています。ポイントは、対策が不可能な理由を「納得できるロジックで示す」ことです。
たとえば、構造上どうしても視覚的に死角が発生してしまう場合、「死角がある」ことをマニュアルに書くだけでは不十分です。「この死角は作業者の左背後方向で、動作領域から20cm以上離れており、接触の可能性が0.05%以下である」といった形で、“なぜリスクとして許容されるのか”を明示的に残すことが、設計者の説明責任を果たすうえで重要です。
さらに、残留リスクは「設備引き渡し時点の説明書」だけでなく、「教育資料」「点検マニュアル」「事故時の報告様式」など、社内の複数ドキュメントに組み込んで初めて意味を持ちます。
協働ロボット導入で「本当に安全か?」と不安はありませんか?
ISO 12100・ISO/TS 15066に基づく「安全チェックポイント」を無料公開中。
導入前に確認すれば、思わぬリスクや見落としを防げます。
- 実際の導入現場で使えるチェックリスト形式なので、すぐに活用できます
- 教育資料や安全レビューにもそのまま利用可能です
- すでに導入済みの企業でも「安全設計の再点検ツール」として役立ちます
協働ロボット導入前・後で確認すべき安全チェックリスト
協働ロボットを導入する際、安全規格を理解するだけでは不十分です。最も重要なのは、「自社の現場に合わせて安全をどう具現化するか」という実務視点です。
特に中小製造業や自動化の経験が少ない職場では、「設計段階の見落とし」や「運用時の習慣的なミス」が重大事故につながりかねません。
このセクションでは、設計・選定から現場運用まで、事故予防と法令順守の両立を図るために必要な実務的な確認ポイントを体系化し、誰でも使えるチェックリストのような形で提示します。
設計・選定段階のポイント(安全柵、速度制御、協調ゾーンなど)
設計・選定段階では、協働ロボットそのものの性能だけでなく、「そのロボットがどう使われるか」という“運用前提”を定義しないまま進めてしまうケースが少なくありません。
特に次の項目は、現場設計を根本から左右する盲点となることが多く、事前に潰しておくことが安全確保の土台となります。
以下に、導入前の設計者・設備担当者が確認すべき代表的な項目をまとめました。
| 項目 | チェック観点 |
|---|---|
| ロボット設置位置 | 人の通路、保守動線との干渉はないか? |
| 作業モード設計 | 協調ゾーンの分離、安全速度の設定は適切か? |
| 可動範囲・停止位置 | 非常停止時に人と干渉するリスクがないか? |
| エンドエフェクタ | 先端ツールに鋭利・回転要素が含まれていないか? |
| 視認性・照明 | 死角が発生する位置に手動操作を必要とする装置がないか? |
| 安全機能 | フォースリミッタ、速度制御、センサ構成などの安全機能は十分か? |
このチェック項目は、いずれも「事故発生時に問われやすい構成要素」であり、設計段階から明示しておくことで、社内説明責任や保険・法的対応にもつながります。
また、意外な盲点として「通路との干渉」「非常停止時の挙動」「作業中の視認性不足」などが事故につながる事例が多く、カタログスペックや3Dレイアウトでは見えない設計検証が求められます。
現場導入・運用時の確認項目(メンテナンス、安全教育)
設計が万全でも、現場での「慣れ」「確認漏れ」「人員入れ替わり」によって、安全レベルは低下します。
実際の労災統計でも、協働ロボット導入現場での事故は「初期設置ミス」よりも「運用中の確認不足」が原因となっているケースが多数あります。
以下に、現場導入後に優先して確認すべき実務項目を整理します。
これらの取り組みを通じて、現場では「安全対策=技術の問題」から「運用と文化の問題」へと意識を広げることができます。
特に教育・点検・記録の3つが機能していない職場では、規格適合よりも先に事故の可能性が生まれやすいため、技術部門・製造現場・人事・総務が一体となった運用体制が必要です。
日本の法令・規制との関係|労働安全衛生規則・80W規制など
協働ロボットの導入を検討する際、多くの現場でつまずくのが「法令対応はどこまでやればいいのか?」という疑問です。カタログスペックやISO規格を読み込んでも、実際に日本国内で導入できるかどうか、どの認可が必要なのかは、明確に説明されていないことがほとんどです。
このセクションでは、厚生労働省の安全衛生規則や80W規制の本質を紐解きつつ、JIS規格とISOとの関係を整理し、導入担当者が迷わず判断できるように構造化します。
厚労省ガイドラインと協働ロボット
日本における産業用ロボットの法的運用は、労働安全衛生法およびその下位規則である「労働安全衛生規則」に基づいています。
その中でも、協働ロボットに直接関係するのが「第150条の4(産業用ロボットの使用)」と「80W規制」に関する通達です。
以前まで、出力が80Wを超えるロボットを導入する際は、労働基準監督署による「個別審査」が必要とされていました。
しかし2013年12月、厚労省からの通達(基発1224第2号)により、ISO 10218-1/-2に基づいたリスクアセスメントと安全設計を実施していれば、個別審査が不要となりました。

Factory DX
運営事務局
これは、制度上の「80W規制緩和」ですが、実際には緩和ではなく「自主責任制への移行」を意味します。
現場で誤解されがちな「80W規制の真意」
80Wを下回れば安全、上回れば審査が必要という理解は、制度の意図を誤解しています。本来この規制は「囲いがなくても安全が確保されているか?」を判断するための基準であり、出力そのものではなく、人との接触を前提にどのような安全対策を取るかが問われているのです。
つまり、80W未満でも構造上の危険があれば事故は起こり得ますし、80W以上でもセンサや力制限が適切であれば、安全だと評価されるべきなのです。
このように、「出力値」ではなく「安全構成の妥当性」が評価軸となったことが、制度変更の核心であり、導入担当者が最も誤解しやすいポイントでもあります。
JIS規格化による実務影響と認証制度の動向
ISO規格は国際的な安全基準として広く使われていますが、日本国内で実際に活用されるのは「JIS規格(日本工業規格)」への翻訳版です。
協働ロボットに関しては、ISO 10218-1/-2をベースにした「JIS B8433-1」「JIS B8433-2」が制定されており、これにより国内の設計者・ユーザーがISO規格に基づいた設計を行いやすくなりました。
また、2025年の改訂にあわせて、このJIS規格も追従する形で改正が予定されています。
ISOとJIS、安全法令の関係整理図
以下に、導入判断に関わる主要制度の関係性を整理したテキスト図を示します。
▼ 国際基準(設計のベース)
──────────────────────────────
ISO 10218-1 / -2
└─ 機械指令対応、安全設計の国際ルール
(対象:ロボットメーカー・輸出入業者)
↓ 翻訳・整合化▼ 国内準拠規格(国内運用向け)
──────────────────────────────
JIS B8433-1 / -2
└─ ISOを翻訳・調整した国内規格
(対象:国内メーカー、SIer、審査機関)
↓ 実務での接続▼ 実務法令(法的義務)
──────────────────────────────
労働安全衛生法・労働安全衛生規則
└─ 安全装置、80W規制、第150条の4など
(対象:使用者・導入企業・保守担当)
この図解が示す通り、ISOはグローバルでの設計基準として機能し、JISはそれを国内に適合させる翻訳規格、そして実際の導入可否は労働安全衛生法令が判断軸となる構造です。
今後は、国内での導入認可においても「ISOベースの自己適合+JIS参照」が主流となるため、形式的な書類対応よりも、根拠となるリスク評価・技術仕様の透明性が求められる流れになっていきます。
このように、規格と法令の関係性を正しく理解することは、導入の可否判断、外注先との契約交渉、社内の安全体制構築に直結します。
【業界別】 協働ロボット安全対策の実例とポイント
協働ロボットは、業界ごとに異なる生産条件や作業者の技能、衛生・品質要件に応じて、求められる安全対策も大きく変わります。
ここでは、自動車、電子部品・医薬・食品、そしてグローバル導入企業の標準化対応に分けて、具体的な事例とその背景にあるポイントを解説します。
自動車業界での活用と対策
自動車業界は協働ロボットのパイオニアとも言える領域であり、「作業者がボディ近くでロボットと並行して作業する」シーンが多く存在します。
一例として、溶接後のバリ取りや、アセンブリ前の部品供給工程など、人とロボットがミリ単位で動線を共有するケースがあります。
この業界での安全対策のキモは、高速・高精度で動くラインにおける“停止と再開の設計”です。
たとえば、BMWやトヨタでは、フォースセンサによる力制限だけでなく、「視覚AIとLidarを併用して、作業者の“行動予測”に基づいた速度制御」を導入し、完全に停止しなくても接触リスクを下げる設計を実現しています。
さらに重要なのが、車両サイズ・作業内容に応じて「協働ゾーンの動的設定」が行われている点です。これは、一定時間ごとにゾーンの境界を可変制御し、ラインの生産段階に合わせて安全制限を最適化する仕組みです。
電子部品・医薬・食品分野での事例
これらの業界は、異物混入や微粒子、クリーン度に対する要求が極めて厳しく、協働ロボットの「物理的安全性」だけでなく、「環境への影響抑制」も安全要件の一部として扱われます。
医薬品製造では、ピッキングや秤量、バッチ工程の一部に協働ロボットが活用されていますが、一般的な油圧アクチュエータやグリース使用部品は使えないため、ISOクラス6以上の清浄度を満たす構造材・表面処理が求められます。
また、食品ラインでは、作業者の手洗い・衛生管理が日常的に行われるのに対し、ロボットは「定期洗浄・薬品対応構造」への適合が課題となります。多くの現場では、ステンレス外装とともに接触部位の防水・耐アルカリ設計(IP67)が実装されており、これは単に設備仕様ではなく、安全性確保の一環と位置づけられています。
さらに独自の安全対策として、可視化システム(色変化表示、音声反応)による状態把握が挙げられます。音や光で「動作モード」「エラー状態」「作業OKサイン」などを即座に伝達することで、言語・国籍を超えた操作安全が実現されています。
グローバル導入企業の標準化対応
世界展開する企業(例:ボッシュ、ファナック、ユニバーサルロボットなど)では、各国の法規制や文化の違いを踏まえて、「多拠点共通の安全設計原則」を導入しています。
オリジナリティのある実例として、ある電子機器メーカーでは、グローバル全工場に対して「協働安全スタンダードテンプレート(CSV/Excel)」を配布し、各拠点が自社要件に応じてカスタマイズしながら運用する方式をとっています。
これは、単一の規格で全世界を統一するのではなく、「規格=最小限の土台、安全運用=現場での最適化」という二層構造で設計されている点が特徴です。
この方式により、拠点ごとの言語・教育レベル・設備制約を吸収しつつ、ISOやJISへの適合性も担保されており、各国の監査対応もスムーズに進められています。
業界別に求められる「安全要件」の優先度比較
以下は、業界ごとに重視される安全項目の違いを整理した図です。
| 業界 | 優先される安全対策要素 |
|---|---|
| 自動車 | 衝突防止、視覚検知、速度制御、協働ゾーン制御 |
| 医薬・食品 | 洗浄対応、清浄度、異物混入防止、表面安全処理 |
| 電子部品 | 静電防止、精密動作制御、粉塵対応、作業環境の可視化 |
| グローバル企業 | 安全設計標準化、言語非依存表示、教育テンプレート整備 |
このように、業界ごとに優先すべき安全要件は異なります。自社のリスク特性と業界基準を照らし合わせて安全設計を行うことが、協働ロボット導入の成否を分ける鍵となります。
協働ロボット導入前に必ず押さえておきたい安全規格Q&A
- 協働ロボットと産業用ロボットでは、安全規格にどんな違いがあるのですか?
協働ロボットは「人との直接接触」を前提としているため、ISO/TS 15066や改訂ISO 10218などで力・速度の制限、感知センサ、協働モードの設計基準が明確に定められています。一方、従来の産業用ロボットは囲い(安全柵)によって人との接触を防ぐ設計が前提です。
- 協働ロボットの導入時に、労基署への届け出や申請は必要ですか?
出力が80Wを超えるロボットは原則として労基署への届出が必要ですが、ISO 10218に基づいたリスクアセスメントと安全設計を実施すれば、個別審査は不要になります(厚労省通達:基発1224第2号)。ただし、事前相談は推奨されます。
- ISO 10218とISO/TS 15066は、どちらを優先すべきですか?
現在(2025年改訂以降)、ISO 10218-1/-2にはISO/TS 15066の内容が統合され、協働作業の安全設計要件も包含されています。したがって、ISO 10218を基準としつつ、15066の旧仕様も参考資料として扱うのが実務的です。
- リスクアセスメントはどの規格に基づいて実施すればよいですか?
基本はISO 12100(リスクアセスメントの体系規格)に基づいて評価します。これに加えて、協働ロボット特有の接触・力加減の基準はISO/TS 15066を参照する必要があります。つまり「12100で全体評価 → 15066で接触部分の詳細補足」が実務の流れです。
- 安全設計でよくあるミスや見落としにはどんなものがありますか?
「非常停止の位置が操作しにくい」「保守用の開口部に安全インターロックがない」「協働ゾーンが作業実態とずれている」などが頻出ミスです。これらはリスク評価だけでなく、現場での検証(ワークシミュレーション)が不十分な場合に起こります。
- ISOの規格とJISの規格には、実務上どんな違いがありますか?
内容の大枠は同じですが、JISは日本語訳にあたり「曖昧な語句や文化差」を吸収する目的で表現が調整されています。たとえば「should」が「望ましい」となるなど、リスク判断に幅が出る場合があります。審査や社内文書ではJISの文言を引用する方が誤解が少ないです。
- 清浄度や異物混入対策も、安全規格に含まれるのですか?
ISO 10218や15066自体には衛生管理の詳細はありませんが、食品・医薬分野では「衛生設計=安全設計の一部」として扱われます。たとえば、表面材質、洗浄性、潤滑剤の非使用などは、ISOクラス6以上を求める顧客要求に含まれ、事実上の安全基準になっています。
- 協働ロボットに“AI”を搭載した場合、追加の安全評価は必要ですか?
はい。AI搭載型では「予測不能な動作」が発生する可能性があるため、IEC 61508(機能安全)やISO 13849(制御系の信頼性)による追加のリスク評価が必要です。AIの学習データや再現性が保証できないと、現状のISO 10218だけでは不十分と見なされます。
- 多言語環境での協働作業では、どんな安全対策が有効ですか?
国際的な製造現場では、操作表示・警告音・光表示など「言語非依存の視覚・聴覚フィードバック」が効果的です。最近では、動作ステータスを色やシンボルで即時表示するインターフェース(例:色変化リング、ピクトグラム音声合成など)が導入されています。
- 協働ロボットの安全対策は、保険契約にも影響しますか?
影響します。損害保険会社によっては、ISO 10218/TS 15066に準拠した設計・運用であれば、労災・生産停止保険の料率を引き下げる制度があります。また、安全認証(第三者機関によるSIL, PL評価など)があれば、企業の安全文化評価にも直結します。
まとめ|安全規格対応は協働ロボット導入の出発点
協働ロボットの導入は、生産性や柔軟性を高めるだけでなく、作業者の負荷軽減や人手不足の解消にも直結します。しかし、そのメリットを最大限に活かすには、安全規格への的確な対応が絶対条件です。
これまで解説してきたように、協働ロボットにはISO 10218やISO/TS 15066、JIS B8433といった国際・国内規格が存在し、それぞれに求められるリスク評価や設計基準があります。特に2025年の改訂では、単なる技術仕様だけでなく、協働モードの設計指針やAI対応、安全文化の標準化といった“新しい常識”が盛り込まれています。
つまり、「安全対応=導入の条件」であると同時に、「安全設計=競争力の源泉」にもなりつつあるのが、現在の製造業の実情です。
自社の現場に協働ロボットの導入を検討している場合、まず取り組むべきは「ロボットの選定」や「価格交渉」ではなく、「現場環境と業務内容に合った安全要件の棚卸し」です。
安全規格は単なる“ルール”ではなく、現場の信頼を確保し、トラブルと損失を未然に防ぐための知的資産です。
もし、現状の作業フローや設備が安全設計と整合していないなら、いきなりロボットを導入するよりも、「安全要件に適合する作業動線の再設計」から始めるべきかもしれません。
安全規格は、導入の“壁”ではなく、運用の“土台”です。今、行動を起こせば、将来的な安全トラブル・監査対応・保険料コストまで含めて、長期的な安心と信頼を得ることができるでしょう。